
渡来系の寺を考える
─檜隈寺跡を題材に─
近畿大学 網伸也先生
(13.6.14発行 Vol.163に掲載)
 |
1.はじめに
飛鳥の渡来系寺院として、東漢一族の氏寺である檜隈寺が有名である。檜隈寺の文献資料での初見は、朱鳥元年(686)8月に100戸の食封を賜った記載で、同じ渡来系寺院である軽寺と大窪寺ともに施入されていることは興味深い。また、この時の食封は天武天皇9(680)年4月の勅を受けて30年を限りとされており、このような期限付き食封は寺院造営にかかわるものと考えられている。ここでは、発掘調査が進んでいる檜隈寺跡の諸要素を分析し、渡来系寺院の特徴を探っていきたい。
2.檜隈寺の伽藍構成
まず、発掘調査で明らかとなった檜隈寺の特異な伽藍に着目したい。発掘調査の結果、塔を中心として、南に石積下成基壇をもつ二重基壇の金堂、北に瓦積基壇の講堂を配する西向きの特異な伽藍であることが判明した。
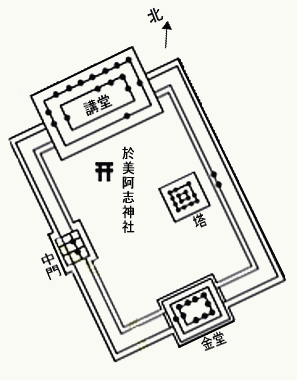
檜隈寺伽藍配置 |
このような塔を中心とした特異な伽藍は今のところ類例がないが、私は山背の樫原廃寺(かたぎはらはいじ)が同様の伽藍を持つ寺院だと考えている。
樫原廃寺は、八角形瓦積基壇をもつ塔と南側に仏堂をもつ寺院になる可能性が高い。樫原廃寺は檜隈寺とは反対に東に開けた立地であり、古道からの景観を考えても塔を中心とする東向きの寺院と考えるほうが理解しやすいのだ。樫原廃寺の造営には秦氏が深くかかわっていると考えられており、渡来系寺院の中に塔を重視する特異な伽藍が存在したと思われる。
3.渡来系氏族と瓦積基壇
渡来系寺院を代表する基壇外装として瓦積基壇がよく知られている。ところが、飛鳥では瓦積基壇はほとんど採用されず、檜隈寺講堂が唯一の例となっている。なぜ、飛鳥では瓦積基壇が採用されなかったのであろうか。
飛鳥の寺院は石積基壇が主流であり、百済の影響として二重基壇もある。瓦積基壇は百済では中心伽藍でも採用されているが、基本的に付属堂舎で多く採用される基壇外装であった。そして、何よりも飛鳥は石敷き広場や石組苑池など、伝統的に石を多用する地域性をもっていた。瓦積基壇は政権の所在地が飛鳥から離れ、難波や近江など渡来系文化が濃厚な地に遷ったときに多く採用されたのであり、そのような景観は飛鳥では忌避されていた可能性が高い。
ところが、檜隈寺の造営にあたっては、講堂の建立で敢えて瓦積基壇を飛鳥で現出させた。天武天皇6(677)年6月に、東漢氏は天皇から代々に渡る七つの不敬を指摘され、強く戒められているが、そのような中で造営された檜隈寺で瓦積基壇が採用された背景に、何か東漢氏の強い思いを感じるのである。
4.檜隈寺の瓦について
発掘調査で判明した檜隈寺伽藍の創建瓦は、金堂で多量に出土した輻線文(ふくせんもん)縁複弁蓮華文軒丸瓦と三重弧文軒平瓦のセットである。

輻線文縁複弁蓮華文軒丸瓦と三重弧文軒平瓦
(奈良文化財研究所藤原宮資料室展示品) |
これらの瓦の年代観については、先の朱鳥元年の食封施入前後と考えられているが、私は壬申乱後の飛鳥浄御原宮遷都を契機として伽藍整備が進められたと睨んでいる。そして、食封施入をうけて藤原宮期の軒瓦で葺かれた塔と講堂の造営が行われたという考えだ。輻線文縁複弁蓮華文の年代については、近江との関係から飛鳥還都後に置くのが妥当であろう。
また、檜隈寺では素弁系あるいは単弁系の天武朝以前の瓦が出土する。とくに、単弁系軒丸瓦は弁に火炎文が認められ、同笵瓦が安芸横見廃寺や明官地廃寺に分布する。発掘調査では下層伽藍は発見されていないが、檜隈寺は7世紀中ごろには寺院として機能していた可能性が高い。

素弁系・単弁系の瓦
(奈良文化財研究所藤原宮資料室展示品) |
安芸への瓦笵の移動の背景には、白雉元(650)年に倭漢直縣(やまとのあやのあたいあがた)らを安芸に使わして百済船を造らしめたことが契機となったと考えられているが、倭漢直縣はさかのぼって舒明朝の百済宮および百済大寺造営を主導した大匠であった。また、難波宮の將作大匠として荒田井直比羅夫が重要な役割をはたしており、7世紀中ごろに造営官として活躍した東漢氏が飛鳥の本拠地に寺院を造営したことは十分想定できよう。
5.おわりに
以上、檜隈寺を題材として渡来系寺院の様相を考えてみた。そこには、一般の古代寺院とは異なる、東漢氏の独自性がさまざまな形で表出しているようである。ただ、檜隈寺の伽藍についてはまだまだ不明な点が多く、下層伽藍についてはまったくわからない状況である。今後の調査によって少しでもその実態が解明されれば、さらに興味深い事実がみえてくることであろう。
|