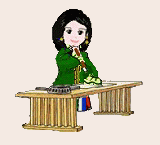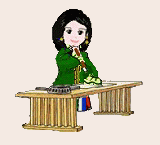|
TOM
「斎王と斎宮と斎宮制度」
斎王とは天皇に代わって天照大神の言葉を聴く御杖代のことです。斎宮とは斎王が住む場所を指します。斎宮制度とは斎王が卜定されてから斎宮に赴き伊勢神宮を拝謁する仕来りを制度化したものです。
第10代崇神天皇のとき都に疫病が蔓延します。コレラか天然痘ではなかったかといわれています。時の朝廷はその原因を求めたところ、朝廷に数々の神々を一緒に祀っていることが原因ではないかと判断します。そこで大物主命は三輪山の大神神社に、倭魂命は大倭神社に、天照大神は倭の笠縫邑に夫々祀ることとします。疫病も神々も落ち着きますが、天照大神だけが居心地が悪いのか落ち着きません。崇神天皇は皇女豊鍬入媛命を御杖代として天照大神に仕えさせますが、崇神天皇の存命中には落ち着く場所を得ないまま次の垂仁天皇の時代に入ります。垂仁天皇は皇女の倭媛命を御杖代として安住の地を捜し求めますが、ここで方針を変更し人が神様の落ち着く場所を探すのではなく、神様から託宣のあった場所を探すことにします。そして倭媛命が五十鈴川の辺まで来たとき託宣を得、ここを安住の地とし伊勢神宮を建てます。従い書紀に従えば初代斎王は豊鍬入媛命であり、同じく伊勢神宮での初代斎王は倭媛命となります。
予断ですが第21代雄略天皇のとき、やはり託宣があり天照大神の食事を司る神として豊受神が伊勢に遣わされます。これが現在の外宮と言われているところです。もちろん女性神ですが、何故か外宮の造りは陰陽道で言う「陽」の造りとなっています。これはおそらく元々男性神を祀っていた神社を外宮としてしまった為ではないかと言われています。
さて壬申の乱で必勝祈願を伊勢神宮にし、勝利を収めた大海人皇子は翌年天武天皇として即位します。大願成就した天武天皇は、伊勢神宮を顕彰して用明天皇から途絶えていた斎王を選出し伊勢に向かわせます。このとき制度化されたものが斎宮制度と言われるもので、以後、後醍醐天皇の時代まで660年間に渡り60人以上の斎王を出すこととなります。天武天皇によって選出された斎王は、娘で未婚の年長である大伯皇女であったことから、斎宮制度が制度化された初代斎王は大伯皇女と言われています。
斎宮制度の内容は平安時代に作られた延喜式に見ることができます。先ず卜定という亀卜によって、神祇官が選任された斎王の適否を占います。どうやら「適」と出るまで繰り返したようで、後には「卜定される」と言えば「斎王に決まる」という意味を持つようになります。欧州の神様は一旦決めたら絶対ですが、日本の神様は何度も頼めばそこまで言うならと妥協する訳です。こんなところのも文化の違いが見出されて面白く思われます。卜定で適となるとその旨太政官に報告がなされ、天皇が改めて斎王となることを勅定します。勅定された斎王は宮廷内にある初斎院に向かい潔斎をしたのち、野宮(ののみや)と呼ばれるところで約1年斎宮での生活を学びます。神社ですから仏教語は使わないよう躾があるわけです。翌年9月の神嘗祭に向けて都を経ちます。このときの儀式を「発遣の儀」と言います。天皇は非公式の白装束で斎王に向かい、「都におもむきたまうこと勿れ」と言って、櫛を前髪に挿します。最後の別れの儀式です。その後、伊勢までは5泊6日の旅であったと伝えられています。頓宮と呼ばれる仮の宿を経て伊勢に向かいます。これを郡行と言います。鈴鹿のほうを通って行く訳ですが、役が終って帰京するときも同じ道となります。但し凶事で帰京するときは名張のほうを通る別ルートに変えられます。何れの場合も一旦、難波津で禊してから入京したそうです。
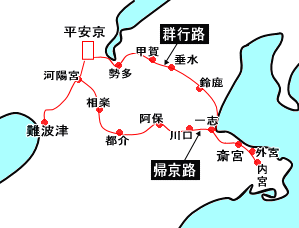 |
斎宮での生活は精進潔斎と言うよりは、歌を詠んだり貝殻の絵合わせで遊んだり各節句を楽しんだりするかなり優雅なものであったようです。伊勢神宮参拝は年に3度、6月12月の月次祭(つきなみさい)と9月の神嘗祭だけだったようです。現在、斎宮跡は昭和45年から発掘調査され続けています。場所は伊勢と松阪の丁度真ん中辺り、伊勢から20km位のところにあります。近鉄山田線の「斎宮(さいくう)」と言う駅のそばにあります。跡地は整備されており、官僚たちの住まい跡なども見ることが出来、奥には「斎宮博物館」があり当時の生活ぶりを体験できるようになっています。伊勢に行かれることがあったら、少し足を伸ばして斎宮跡を見学するのもいいかも知れません。
|