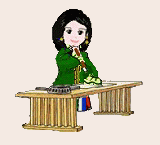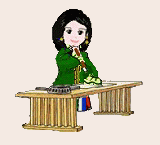|
河内太古
橘寺の伽藍配置と二面石について ・ 飛鳥の謎石の「立石」について
「橘寺の伽藍配置と二面石について」
飛鳥を訪問された人は、何度か橘寺に立ち寄られ、ご本尊にもお参りされ、飛鳥の謎石とされる境内の二面石はよくご存じだと思います。橘寺のご本尊は聖徳太子像ですが、太子のどんなご尊像であったか、正確に記憶しておられるでしょうか? 太古もこれまでに何度か本堂に上がっているのですが、薄暗い本堂の奥の方に安置されていますので、あらためて問われると、どんなお姿であったか極めて曖昧であることに気付きました。
ご本尊の太子像は「聖徳太子勝鬘経講讃像」で、国の重要文化財に指定された室町時代の坐像です。太子が推古天皇に勝鬘経の講義をされた35歳のお姿を現わしていると伝えられています。
聖徳太子が生まれた年は、日本書紀によると敏達天皇の3年(西暦574年)1月となっていますが、聖徳太子信仰のバイブルとなった平安時代後期に著された「聖徳太子伝暦」では敏達元年1月とされています。このため、推古天皇に勝鬘経の講義した時の太子の年齢は、33歳とも35歳ともなるのですが、橘寺は「伝暦」に基づく年齢で尊像の表記がなされています。
この「聖徳太子勝鬘経講讃像」の太子は、左手に「塵尾(しゅび)」と称される珍しい法具を執っています。手に香炉を持って父・用明天皇の病気平癒を願う16歳時の太子孝養像はよく知られていますが、この左手に塵尾(しゅび)を執るのが太子講讃像の特徴だそうです。塵尾(しゅび)は正倉院御物にもあるそうですが、まだ見たことはありません。
今度、橘寺にお参りされた時は、ぜひじっくりとこのご本尊をご覧頂きたいと思います。
この橘寺には二面石と呼ばれる飛鳥の謎石のひとつがあります。二面の彫りを持ち、向かって右側が善面、左側が悪面とされ、人の心の持ち方の二相を表しているとされています。二面石がいつごろから橘寺に置かれたかは不明ですが、当初から境内にあったものではなく、他所から移設されたものです。猿石や人頭石と同じところから掘り出されたとする説もありますが、現在吉備姫王墓にある猿石4体のような明確な記録はないようです。人の善悪の二相を表すとする二面石は、橘寺境内に置かれているのが最も似つかわしいような気がします。
この二面石が置かれている場所には、現在の本堂と合わせ橘寺の講堂が位置していたことが、昭和28年以降の発掘調査によって判明しています。この講堂跡から東に向かって金堂、塔、中門が一列に並び、周囲を回廊が巡るいわゆる四天王寺式の伽藍が配置されていたと考えられていました。
ところが、その後の発掘調査で講堂跡の東側に西面が揃う凝灰岩の地覆石の石列が検出され、この石列が回廊跡の一部だとすると、回廊が金堂の後ろで閉じていた可能性が高くなっています。古代寺院の伽藍配置図をご覧頂いただくと、講堂、金堂、塔、中門が一列に並ぶ伽藍配置のうち、講堂が回廊の外に配置するのが山田寺式伽藍配置です。
検出された石列が短いため確たる証拠にはならないようですが、昭和54年に橿原考古学研究所が講堂に取り付いていたと思われる回廊の北側位置を発掘したところ、回廊跡の痕跡が見いだせなかったこと、さらには、講堂が奈良時代に建設されているとする寺伝からすると、その後に伽藍配置が確認された山田寺式伽藍配置であった可能性が高くなっています。ただ、検出された石列があまりにも講堂跡に近接しているために、回廊が金堂と講堂の間を巡っていたとするには、更なる考古学的検証が必要なようです。
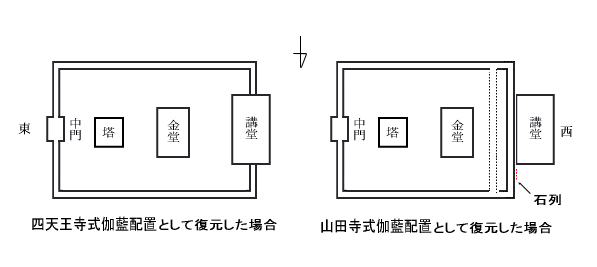 |
「飛鳥の謎石の「立石」について」
甘樫丘の北麓の豊浦の地に「甘樫坐神社」という古社が鎮座しています。推古天皇の豊浦宮跡で知られる向原寺の本堂の西側に、里道を挟んで接しています。
この神社の境内では、古代の裁判の一種であったとされる「盟神探湯(くがたち)」神事が、毎年4月の第1日曜日に、豊浦・雷の氏子さん達によって模擬的に再現されています。
神事は「豊浦の立石」と呼ばれる大きな自然石の前に釜を据えて、古代裁判を模した再現劇が実演され、うそ偽りのない爽やかな暮らしを願って、飛鳥坐神社宮司によるご祈祷が執り行われています。もちろん、実際に煮えたぎる釜湯の中に手を入れることはできませんから、笹の葉を入れてその色の変化で代替しています。心に疚しさがあると笹の葉の色が変わるそうですから、皆さんも一度お試しになられてはいかがでしょうか。
境内に設置された「盟神探湯」の解説板には、この立石は、豊浦のほかに明日香村内のいくつかに残されていて、岡、上居、立部、小原の箇所名が列記されています。このうち「小原の立石」だけは所在が分からなくなっていますが、かっては存在した「小原の立石」が今はないとまでは言い切れないようです。これが「小原の立石」だ分かる日が待たれます。
「川原の立石」は、発掘された後は埋め戻され、今は飛鳥川にかかる高市橋手前の飛鳥周遊路の地下に埋まっています。発掘される前は地上に30センチ(全高1.55m.)ほど頭が出ていたそうです。発掘時の写真を見ますと、砂礫層に立てられているため、立石の安定を保つため人頭大の根石4個が据えられていました。この立石が据えられていた場所は、大和条理高市郡東30条4里5坪にあたり、川原寺の寺域の境になるそうです。
立石が何のために立てられたのかは定説がありません。飛鳥の京域を示したものとか、寺域を示したものとか、条里制以前の地割りの位置を示したものではないかといわれていますが、川原の場合は川原寺の寺域を示したものとも考えられます。
「岡寺の立石」は、仁王門前の左の細い山道を上ると、岡寺の山中に巨大な石が立てられています。この石を最初に見たときは、思わず自然に「立っている」 と思ったものですが、人為的に「立てられている」からこそ「立石」(たていし)なんでしょうね。なお、この立石のある場所への山路が通行止めになっていますので、今は近づくことはできません。
「上居の立石」は、石舞台横の道路を細川方面に向かう途中、上居バス停から少し前方の左側の里道に沿ったところに見ることができます。次回の定例会ウォーキングではこの立石も訪ねることにしています。
「立部の立石」は、立部にある定林寺跡で見ることができますが、雑草が生い茂ると隠れてしまいそうな小さな石です。石の形は川原の立石と良く似ているような気がしますが、これが立石かと思うほど、何の変哲もない石です。
立石はこのほかにも、飛鳥の「弥勒石」や祝戸の「マラ石」も挙げられる場合がありますが、これらの石は自然石を立てたものではなく、明らかに人為的に細工された石造物です。飛鳥は、立石や猿石をはじめ、さまざまな謎石に満ちた古代ミステリーゾーンです。往古の人が何のために石を置き、石に何を刻もうとし
たのか、謎石を訪ねながら石に託された古代人の思いに想像を巡らすのも楽しい歴史ハンティングではないでしょうか。
|