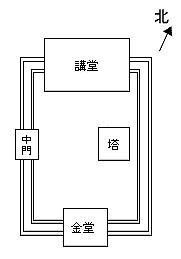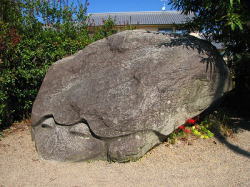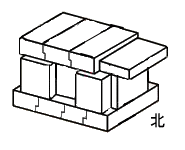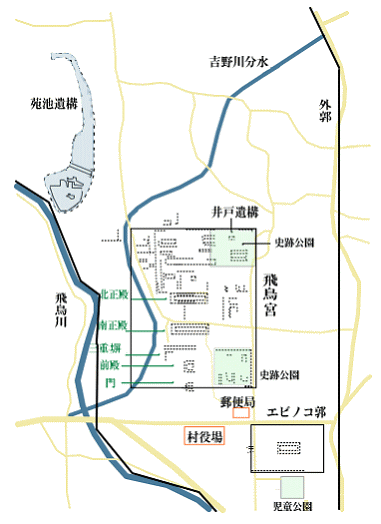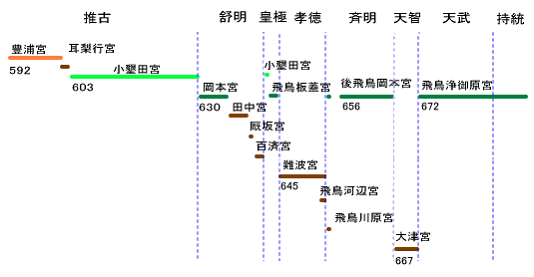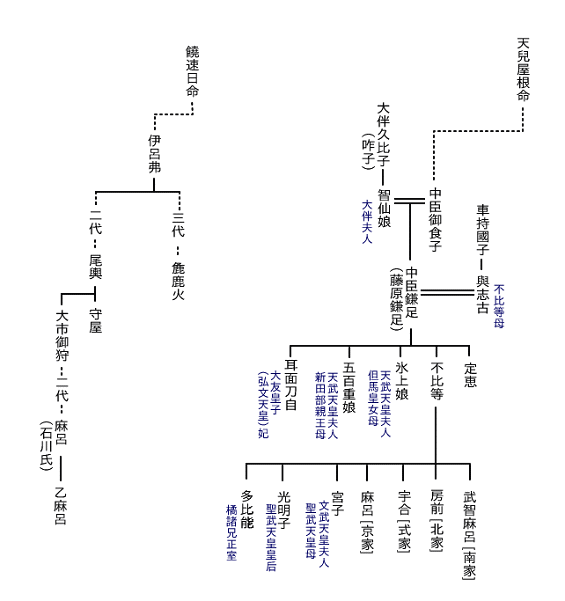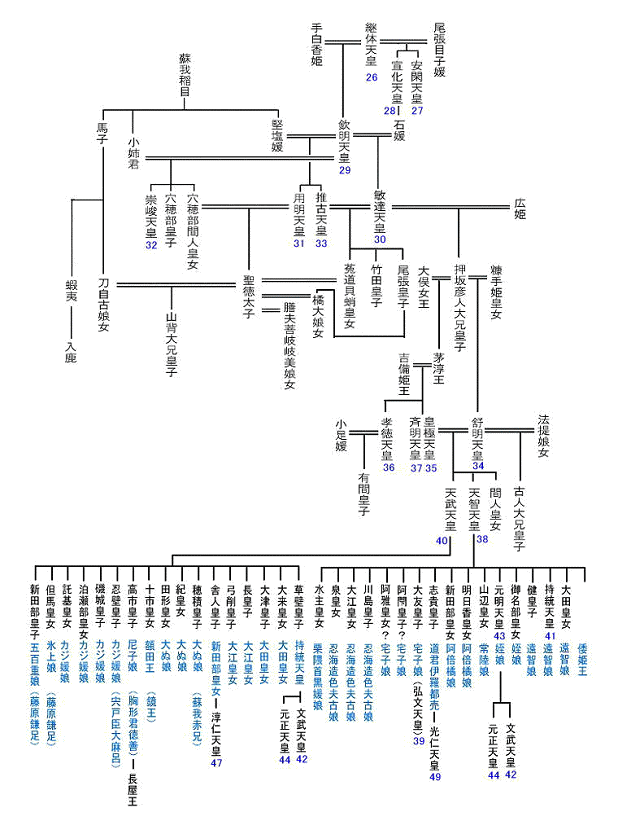پ@”ٍ’¹’nˆو–k•”ٹT—ھگ}پiƒNƒٹƒbƒN‚إ•تƒEƒBƒ“ƒhƒE‚ھٹJ‚«‚ـ‚·پj‚ًŒ©‚ب‚ھ‚çپA‚S‘ً‚ج’†‚©‚çٹY“–‚·‚éˆâگصپEژjگص‚ج’nگ}ڈم‚ج”شچ†‚ً‚¨‘I‚ر‚‚¾‚³‚¢پB
–â‚Pپ@پ@پ@”ٍ’¹ژ‘م‚حپAگ„Œأ“Vچc‚ھ”ٍ’¹’nˆو“à‚ج‹{‚ة‘¦ˆت‚µ‚½‚T‚X‚Q”N‚©‚çپA‚V‚P‚O”N‚ج•½ڈé‹‘J“s‚ـ‚إ‚ج–ٌ‚P‚Q‚O”Nٹش‚ً‚³‚µ‚ـ‚·پB‚³‚ؤپA”ٍ’¹ژ‘م‚ج–‹ٹJ‚¯‚ئ‚ب‚ء‚½گ„Œأ“Vچc‚ج‹{‚جˆê•”‚¾‚ئگ„’肳‚ê‚éگخ•~ˆâچ\‚ھŒںڈo‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éڈêڈٹ‚ح‰½”ش‚إ‚µ‚ه‚¤پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi”ٍ’¹’nˆو–k•”ٹT—ھگ}”شچ†ڈئچ‡•\پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚PپFپ@‚Qپi—‹‹uپjپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚QپFپ@‚Sپi–L‰Yژ›گصپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚RپFپ@‚P‚Rپiگخگ_ˆâگصپjپ@پ@ پ@پ@پ@‚SپFپ@‚R‚Wپi”ٍ’¹‹گصˆنŒثˆâچ\پj
پ@–L‰Y‚جŒüŒ´ژ›‚©‚ç“ى‚ة‚©‚¯‚ؤ‚حپA“Œ‘¤‚و‚èˆê’iچ‚‚¢’nŒ`‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¨‚èپA–L‰Y‹{پE–L‰Yژ›‚جگ„’è’n‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پBŒüŒ´ژ›‚جژ›ˆو‚إگ”“x‚ج”Œ@’²چ¸‚ھچs‚ي‚ê‚ؤ‚¨‚èپA‚Vگ¢‹I‘O”¼‚ةŒڑ—§‚³‚ꂽ–L‰Yژ›‚جچu“°‚ئگ„’肳‚ê‚éŒڑ•¨گص‚ھ”Œ©‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@‚³‚ç‚ة‚»‚ج‰؛‘w‚©‚çپAگخ•~‚ً”؛‚¤Œ@—§’ŒŒڑ•¨گص‚ھŒںڈo‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پBŒڑ•¨‚ح“ى–k‚RٹشˆبڈمپA“Œگ¼‚Rٹشˆبڈم‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ھ•ھ‚©‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB”ٍ’¹‚إ”Œ@‚³‚ê‚é‹{“a‚ج“ء’¥‚جˆê‚آ‚حپAŒڑ•¨‚جژüˆح‚ةگخ•~‚«‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚إ‚·‚ھپA‚»‚ê‚ةچ‡’v‚·‚é’²چ¸Œ‹‰ت‚ھڈo‚½‚±‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB

ŒüŒ´ژ›‰؛‘wˆâچ\
|
پ@‚±‚ج‚و‚¤‚ة‚µ‚ؤ“¾‚ç‚ꂽ”Œ@’²چ¸‚جŒ‹‰ت‚حپA‚±‚ج’n‚ة–L‰Y‹{‚ھ‘¢‰c‚³‚êپA‹{‚ھڈ¬چ¤“c‹{‚ة‘J“s‚³‚ꂽŒم‚ةپA–L‰Yژ›‚ھŒڑ—§‚³‚ꂽ‚±‚ئ‚ًژ¦‚µ‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚ةژv‚¢‚ـ‚·پB
پ@ŒüŒ´ژ›‚إ‚ح”Œ@’²چ¸‚³‚ꂽˆâچ\‚جˆê•”‚ھŒِٹJ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBˆâچ\–ت‚ھŒ©‚ç‚ê‚é‚ج‚حپA”Œ@Œ»’nگà–¾‰ï‚ًڈœ‚¯‚خپAŒہ‚ç‚ꂽ‹@‰ï‚µ‚©‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ج‚إپA‹Mڈd‚ب‘¶چف‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پiژQچlژ‘—؟پF”ٍ’¹ژ‘م‚ج‹{‚ج•دٹ·پj
پiژQچlپF–L‰Y‹{پj
–â‚Qپ@پ@پ@–¾“ْچپ‘؛“à‚إ‚حچإŒم‚ج‹{‚ئ‚ب‚ء‚½“V•گ“Vچc‚ج”ٍ’¹ڈٍŒنŒ´‹{‚ج“àٹs–kگ³“a‚ئ‚³‚ê‚éˆâچ\‚ھŒںڈo‚³‚ꂽ‚ج‚ح‰½”ش‚إ‚µ‚ه‚¤پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi”ٍ’¹’nˆو–k•”ٹT—ھگ}”شچ†ڈئچ‡•\پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚PپFپ@‚Vپi‰œژR‹v•ؤژ›گصپjپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚QپFپ@‚Q‚Wپi”ٍ’¹‹گص“ى–kٹîٹ²”rگ…ˆâچ\پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚RپFپ@‚R‚Vپi”ٍ’¹‹گص“àٹsگ³“aگصپjپ@پ@ ‚SپFپ@‚R‚Xپi‹k‹Œژ›ˆوˆâچ\پj
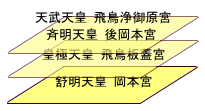 |
پ@‚R‘w‚Sٹْ‚ج‹{گص‚ھڈd‚ب‚ء‚ؤ‘¶چف‚·‚é‚ئ‚¢‚ي‚ê‚é”ٍ’¹‹{گص‚جچإڈم‘w‚ة‚ ‚邱‚جˆâچ\‚حپAچlŒأٹw“I‚ة‚ح‘و‚Rٹْ‚a‚ئŒؤ‚خ‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپAگؤ–¾“Vچc‚جŒم”ٍ’¹‰ھ–{‹{‚ًŒpڈ³‚µ‰üڈC‚µ‚½پA”ٍ’¹ڈٍŒنŒ´‹{‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB |
پ@‚Q‚O‚O‚T”NپA‚Q‚O‚O‚U”N‚ئ‘±‚¯‚ؤ‚Q“ڈ‚ج‘هŒ^Œ@—§’ŒŒڑ•¨پi“Œگ¼‚WٹشپE“ى–k‚Sٹش‚ج“¯‹K–حŒڑ•¨پj‚ھŒںڈo‚³‚êپAگخ•~ˆâچ\‚ً”؛‚ء‚½‚±‚ê‚ç‚جŒڑ•¨‚حپA“àٹs‚جگ³“a‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئ’چ–ع‚ًڈW‚ك‚ـ‚µ‚½پBŒڑ•¨‚ح“ى–k‚ة”ف‚ًژ‚آگطچبژ®‚جŒڑ•¨‚إپAڈ°‘©‚ھŒںڈo‚³‚ꂽ‚±‚ئ‚ة‚و‚èپAڈ°‚ًژ‚آŒڑ•¨‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ھ•ھ‚©‚è‚ـ‚µ‚½پB‚±‚ج’²چ¸‚ة‚و‚ء‚ؤپA“V•گپEژ““Vچc‚ج”ٍ’¹ڈٍŒنŒ´‹{‚ج“àٹs‚ج‚ظ‚ع‘S—e‚ھ–¾‚ç‚©‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB

“àٹs“ىگ³“aگصپi‚Q‚O‚O‚TپD‚RپDپjپ@پ@ پ@ پ@“àٹs–kگ³“aگصپi‚Q‚O‚O‚UپD‚RپDپj |
پiژQچlژ‘—؟پF”ٍ’¹‹ٹضکAˆâچ\”z’uگ}پj
پiژQچlژ‘—؟پF”ٍ’¹ژ‘م‚ج‹{‚ج•دٹ·پj
پiژQچlپF‘و‚Q‰ٌ’è—ل‰ïژ‘—؟پ@–„‚à‚ꂽŒأ‘م‚ً–K‚ث‚éپ@”ٍ’¹‹{پj
پiژQچlپF”ٍ’¹ڈٍŒنŒ´‹{پj
–â‚Rپ@پ@پ@‰³–¤‚ج•د‚ج•‘‘ن‚جˆê‚آ‚إ‚à‚ ‚ء‚½‘h‰ن“üژ“@‚جˆê•”‚ئگ„’肳‚ê‚éپA‚ئ•ٌ‚¶‚ç‚ꂽˆâچ\‚ھŒںڈo‚³‚ꂽڈêڈٹ‚ح‰½”ش‚إ‚µ‚ه‚¤پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi”ٍ’¹’nˆو–k•”ٹT—ھگ}”شچ†ڈئچ‡•\پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚PپFپ@‚Pپi—‹‹u–k•ûˆâگصپjپ@پ@پ@پ@پ@‚QپFپ@‚P‚Qپi•½‹gˆâگصپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚RپFپ@‚P‚Uپiژً‘Dگخپjپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚SپFپ@‚Q‚Tپiٹأٹ~‹u“Œک[ˆâگصپj

ٹأٹ~‹u“Œک[ˆâگص |
پ@”ٍ’¹‚إچإ‚à—L–¼‚بڈêڈٹ‚جˆê‚آپAٹأٹ~‹u‚ج“Œ“ىک[‚ةˆâگص‚ح‚ ‚èپAپuٹأٹ~‹u“Œک[ˆâگصپv‚ئŒؤ‚خ‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚Q‚O‚O‚T”N‚©‚çŒp‘±‚µ‚½’²چ¸‚ھچs‚ي‚ê‚ؤ‚¨‚èپA‘h‰ن“üژ‚جپu’J‚ج‹{–هپv‚ئڈج‚³‚ꂽ“@‘î‚جˆê•”‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئکb‘è‚ًڈW‚ك‚ـ‚µ‚½پB
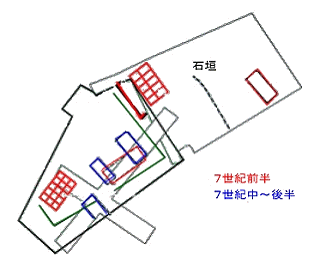
ٹأٹ~‹u“Œک[ˆâچ\گ}
|
پ@‚Q‚O‚O‚T”N‚ج’²چ¸‚إ‚حپA‚Vگ¢‹I‚جŒ@—§’ŒŒڑ•¨گص‚ھ‚U“ڈŒںڈo‚³‚êپA‚Q‚O‚O‚U”N‚©‚ç‚ح–{ٹi“I‚ب”Œ@’²چ¸‚ھژn‚ـ‚èپA’J‚ً–„‚ك—§‚ؤ‚é‘ه‹K–ح‚بگ·‚è“yپA‘½‚‚جŒ@—§’ŒŒڑ•¨گصپAگخٹ_‚ب‚ا‚ھٹm”F‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‹N•ڑ‚ج‚ ‚éژ©‘R’nŒ`‚¾‚ء‚½’J’n‚جˆê•”‚ةپA‚Vگ¢‹I‘O”¼‚ة“y‚ًگ·‚ء‚ؤ•½’R‚ب•~’n‚ً‘¢‚èپAگخٹ_‚ً’z‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB
پ@‚µ‚©‚µپA‚±‚جگخٹ_‚حپA‚Vگ¢‹I’†چ ‚©‚çŒم”¼‚ة–„‚ك—§‚ؤ‚ç‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚·پB |
پ@‚»‚جگص’n‚ة‚حپAچL‚¢•½’R‚ب“y’n‚ھ‘¢‚èڈo‚³‚êپAŒڑ•¨‚ھŒڑ‚؟‚ـ‚µ‚½پB‚»‚جŒڑ•¨‚حژO‰ٌˆبڈمŒڑ‚ؤ‘ض‚¦‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ؤپAٹˆ”‚ب“y’n—ک—p‚ھژf‚¦‚ـ‚·پB‚Q‚O‚O‚W”Nڈt‚ج’²چ¸‚إ‚حپA‚Vگ¢‹I’†چ ‚ج“yٹي‚ھڈo“y‚µپAŒڑ•¨‚ًژو‚è‰َ‚µگ®’n‚µ‚½ژٹْ‚ھ“ء’肳‚ê‚ـ‚µ‚½پB
پ@‚±‚ê‚ç‚ج”Œ@’²چ¸‚جگ¬‰ت‚حپA‘h‰ن–{ڈ@‰ئ‚جگ·گٹ‚ئژٹْ‚ً“¯‚¶‚‚µ‚ؤ‚¨‚èپA‰³–¤‚ج•د‘OŒم‚ج”ٍ’¹‚ج—ًژj‚ً•¨Œê‚ء‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚ةژv‚¦‚ـ‚·پB
پiژQچlپF”ٍ’¹—V–K•¶Œةپ@“ء•تٹٌچeپ@پuٹأٹ~‹u“Œک[ˆâگص‚ج’²چ¸پvپ@“ق•¶Œ¤پ@–L“‡’¼”ژگوگ¶پj
پ@ˆب‰؛‚حپA‚S‘ً–â‘è‚إ‚·پB
–â‚Sپ@پ@پ@”ٍ’¹ژ›‚ة‚حچ‘“àچإŒأ‚ج‹à“؛•§پA’تڈجپu”ٍ’¹‘ه•§پv‚ئŒؤ‚خ‚ê‚éژك‰ق”@—ˆچ؟‘œ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚Q‚O‚O‚W”N‚SŒژ‚W“ْ‚ة‚حٹJٹل‹ں—{‚©‚ç‚P‚S‚O‚O”N‚ًŒ}‚¦پAŒcژ]–@—v‚ھ‰c‚ـ‚ê‚ـ‚µ‚½پB‚³‚ؤپA”ٍ’¹ژ›‚ح‰ك‹ژ‚Q“x‚ج‰خچذ‚ة‘ک‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA‚±‚ج”ٍ’¹‘ه•§‚حگج‚àچ،‚à‚»‚جˆت’u‚ً•د‚¦‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ئŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBŒ»چفپAˆہ‹ڈ‰@‚ئŒؤ‚خ‚ê‚é‚»‚جڈêڈٹ‚حپA‘nŒڑ“–ژ‚ة‚حژں‚ج‚ا‚ج“°‰F‚¾‚ء‚½‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚PپFگ¼‹à“°پ@پ@پ@‚QپF’†‹à“°پ@پ@پ@‚RپF“Œ‹à“°پ@پ@پ@‚SپFچu“°
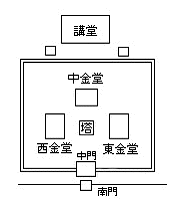
”ٍ’¹ژ›‰¾—•”z’u |
پ@”ٍ’¹ژ›‰¾—•”z’u ”ٍ’¹ژ›‚حŒـڈd“ƒ‚ً’†گS‚ةپA’†‹à“°پA“Œ‹à“°پAگ¼‹à“°‚©‚ç‚ب‚éˆê“ƒژO‹à“°ژ®‚إپA“Œگ¼–ٌ‚Q‚O‚OmپA“ى–k–ٌ‚R‚O‚Om‚à‚ ‚é‘s‘ه‚ب‰¾—•‚ًژ‚ء‚½ژ›‰@‚إ‚µ‚½پB‚»‚جژü‚è‚ة‰ٌکL‚ھ‚ ‚èپA‰ٌکL‚جٹO‚ج–k‘¤‚ةچu“°‚ًگف‚¯‚½‰¾—•—lژ®‚إ‚ ‚ء‚½‚±‚ئ‚ھ•ھ‚©‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@‚µ‚©‚µپAژ›‚ح‚W‚W‚V”N‚ئ“ء‚ة‚P‚P‚X‚U”N‚ج“ƒ‚ض‚ج—ژ—‹‚ة‚و‚é‰خچذ‚ج‚½‚كپA‰¾—•‚ج‘½‚‚ًڈؤژ¸‚µ‚½‚و‚¤‚إ‚·پBŒم‚حگٹ‘ق‚ھ’ک‚µ‚پAچ]Œثژ‘م‚ةچؤŒڑ‚³‚ꂽ‚ج‚ھ’†‹à“°‚ج‚ ‚ء‚½ڈêڈٹ‚ةŒڑ‚ؤ‚ç‚ꂽچ،‚ة‚ ‚éˆہ‹ڈ‰@‚ج‘Oگg“°‰F‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB |
 پ@ پ@ |
| پ@–{‘¸”ٍ’¹‘ه•§پiژك‰ق”@—ˆچ؟‘œپj‚حپA‚U‚O‚T”Nپiگ„Œأ‚P‚R”Nپj“Vچc‚جڈظ‚ة‚و‚èپAˆئچى’¹•§ژt‚ة‘¢‚点‚½“ْ–{چإŒأ‚ج•§‘œ‚ئŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA“ٌ“x‚ة‚ي‚½‚é‰خچذ‚إ‘¹ڈ‚àŒƒ‚µ‚ڈC—‚ًڈd‚ث‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½‚ھ‰ژ‚جژp‚ً—¯‚ك‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚حپA“ھ•”‚إ‚حٹzپE—¼”ûپE—¼ٹلپE•@—ہپAچ¶ژè‚جڈ¶‚جˆê•”پA‰E•Gڈم‚ة‚ح‚كچ‚ـ‚ê‚éچ¶‘«— ‚ئ‘«ژwپA‰Eژè’†ژwپE–ٍژwپEگlچ·ژw‚¾‚¯‚ئŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB–ـک_‚±‚ج‘ه•§‚ح’†‹à“°‚ةˆہ’u‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB |
پi”ٍ’¹‘ه•§‚P‚S‚O‚O”Nچص‚حپAپuŒ³‹»ژ›‰ڈ‹Nپvڈٹˆّ‚جپuڈنکZŒُ”w–ءپv‚ةڈ‘‚©‚ê‚ؤ‚¢‚éپAگ„Œأ“Vچc‚P‚V”Nپi‚U‚O‚Xپj‚ةٹ®گ¬‚µ‚½‚ئ‚·‚éگà‚ة‚و‚è‚ـ‚·پB“ْ–{ڈ‘‹I‚ة‚حپAگ„Œأ‚P‚R”Nپi‚U‚O‚Uپj‚SŒژ‚ةٹ®گ¬‚µ‚½‚ئڈ‘‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپj
پiژQچlپF‘و‚Q‰ٌ’è—ل‰ïژ‘—؟پ@–„‚à‚ꂽŒأ‘م‚ً–K‚ث‚éپ@”ٍ’¹‚جˆâگصپj
پiژQچlپF”ٍ’¹ژ›’TŒںپj
پiژQچlپF”ٍ’¹ژ›گصپj
–â‚Tپ@پ@پ@‚Q‚O‚O‚W”N‚RŒژپA“،Œ´‹{‘ه‹ة“a‰@“ى–هگص‚ج”Œ@’²چ¸‚إپA’n’ء‹ï‚ئ‚µ‚ؤژg‚ي‚ꂽ‚ئژv‚ي‚ê‚镽•r‚ھ”Œ©‚³‚ꂽ‚±‚ئ‚ح‹L‰¯‚ةگV‚µ‚¢‚ئ‚±‚ë‚إ‚·پB‚±‚ج•½•r‚جŒû•”‚ة‚حپA”ٍ’¹’rˆâگص‚©‚çڈo“y‚µ‚½•x–{‘K‚ئ‚حˆظ‚ب‚é•x–{‘K‚X–‡‚ھگً‚ج‚و‚¤‚ة’u‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB‚ـ‚½پA‚»‚ج’†‚ة‚حپA•x–{‘K‚ً’ت‚µ‚ؤگZ‚فچ‚ٌ‚¾‚ئژv‚ي‚ê‚é‰Jگ…‚ئ‹¤‚ةپA‚ ‚é‚à‚ج‚ھ‚XŒآ“ü‚ê‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ھŒ©‚آ‚©‚è‚ـ‚µ‚½پB‚³‚ؤ•x–{‘K‚ئ‚ح•ت‚ةپA•½•r‚ج’†‚ةژc‚ء‚ؤ‚¢‚½‚X‚آ‚ج‚à‚ج‚ئ‚حژں‚ج‚ا‚ê‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚PپFƒKƒ‰ƒXپ@پ@پ@‚QپFƒqƒXƒCپ@پ@پ@‚RپFƒپƒmƒEپ@پ@پ@‚SپFƒXƒCƒVƒ‡ƒE
پ@“،Œ´‹‚ج’n’ءچص‚ج‚±‚ئ‚ح“ْ–{ڈ‘‹I‚ةŒ©‚¦‚éژ“‚T”Nپi‚U‚X‚Pپj‚جپuگV‰v‹پi‚ ‚ç‚ـ‚µ‚ج‚ف‚₱پپ“،Œ´‹پj‚ً’ء‚كچص‚炵‚قپv‚ئپAژ“‚U”Nپi‚U‚X‚Qپj‚ةپuڈٍچLموپi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤‚µپj“ï”g‰¤“™‚ًŒ‚ي‚µ‚ؤپA“،Œ´‚ج‹{’n‚ً’ء‚كچص‚炵‚قپv‚ج‹Lژ–‚ھŒ©‚¦‚ـ‚·‚ھپAچ،‰ٌ”Œ@‚³‚ꂽ‚ج‚ح‚»‚جژ‚ج‚¢‚¸‚ê‚©‚ج‚à‚ج‚¾‚ء‚½‚ئچl‚¦‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@’n’ءچص‚حپA‰A—z“¹‚ة’[‚ً”‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB“ْ–{‚ة‚¨‚¯‚é‰A—z“¹‚حپA•—گ…ژv‘z‚âŒـچsژv‘z‚ًژو‚è“ü‚êپA‹g‹¥‚ًگ肤‹Zڈp‚ئ‚µ‚ؤگ_“¹پA“¹‹³پA•§‹³“™‚ة‚à‰e‹؟‚ًژَ‚¯‚ب‚ھ‚ç“ئژ©‚جٹw–â‚ئ‚µ‚ؤ”“W‚µ‚ؤچs‚«‚ـ‚·پB‚Tپ`‚Uگ¢‹I‚ة“`‚¦‚ç‚ꂽ‰A—z“¹‚حپA“V•¶پE“ظچb‚جچث”\‚ھ‚ ‚ء‚½‚ئ‚³‚ê‚é“V•گ“Vچc‚جچ ‚ة‘ه‚«‚ب‰وٹْ‚ًŒ}‚¦‚ـ‚·پB‰A—z“¹‚حپA—¥—كگ§‚ج‰؛‚ة’u‚©‚êپA‰A—z—¾‚ض‚ئ‘gگD‰»‚³‚êپA‹}‘¬‚ب”“W‚ًگ‹‚°‚ؤچs‚«‚ـ‚·پB
پ@‚X‚ئŒ¾‚¤گ”ژڑ‚ح‰A—z“¹‚ة‚ ‚ء‚ؤ‚حچإچ‚‚ج—z‚جگ”ژڑ‚إ‚·پB•x–{‘K‚ھ‚X–‡ژg‚ي‚ꂽ‚ج‚حپA‚±‚ج“،Œ´‹‚ھ•x‚ة‰h‚¦‚é‚و‚¤‚ةٹè‚¢پA‚»‚ج•½•r‚ج’†‚ةگ…ڈ»‚ً‚X‚آ“ü‚ꂽ‚ج‚حگ…ڈ»‚ھپuگS‚ئ‘ج‚ة“‚«‚©‚¯‚éپw‹Cپx‚ًڈW‚كڈٍ‰»‚·‚éپv‚à‚ج‚ئچl‚¦‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚±‚ë‚©‚çپA‹¤‚ة‚»‚جچإ‚½‚é‚à‚ج‚ًٹè‚ء‚ؤژ·‚èچs‚ي‚ꂽ‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB

•x–{‘KƒŒƒvƒٹƒJ |
پiژQچlژ‘—؟ پF‰ف•¼‚ةٹض‚·‚é“ْ–{ڈ‘‹I‚ج‹Lچع‹y‚ر–³•¶‹â‘K‚ة‚آ‚¢‚ؤپ@پj
پiژQچlپF‘و‚P‚O‰ٌ’è—ل‰ïژ––±‹اˆُ”•\ƒŒƒ|پ[ƒgپ@•x–{‘K‚ئƒAƒ“ƒ`ƒ‚ƒ“‚ئ”ٍ’¹’rˆâگصپj
پiژQچlپF“ق•¶Œ¤ƒjƒ…پ[ƒXNo.28 پu“،Œ´‹{‘ه‹ة“a‰@“ى–هڈo“y’n’ء‹ïپv
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ|“ق—ا•¶‰»چàŒ¤‹†ڈٹپ@ٹwڈpڈî•ٌƒٹƒ|ƒWƒgƒٹپj
–â‚Uپ@پ@پ@چ‚ژsŒSŒأ•ژڈ‚ةپuپcگخط‚ج’†‰›‚ة‘ه‚¢‚ب‚éŒ؛ژ؛‚ً—L‚µپA‘OŒم‚ة‚ح‰½‚ê‚à“Œ‘¤•ا‚ةگع‚µٹeˆêŒآ‚ج‘A“¹‚ً—L‚µپA‚à‚ئ–k•û‚¾‚¯‹ح‚ة™³™´‚µ‚ؤ“à•”‚ةگِ“ü‚µ“¾‚ׂ«Œû‚ًٹJ‚¢‚ؤ‚ ‚ء‚½‚ھپAپcپv‚ئ‹L‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½Œأ•‚ج–{ٹi“I”Œ@’²چ¸‚ھچs‚ي‚êپA‚Q‚O‚O‚W”N‚QŒژ‚ج‘هگل‚ج’†‚إŒ»’nŒ©ٹw‰ï‚ھژہژ{‚³‚ꂽâuâƒڈَ‚ج‰،Œٹژ®گخژ؛‚ً—L‚·‚éŒأ•‚ح‚ا‚ê‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚PپFƒJƒ“ƒWƒ‡Œأ•پ@پ@پ@‚QپFŒ،‹چژq’ثŒأ•
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚RپFڈ¬’JŒأ•پ@پ@پ@پ@ ‚SپFگ^‹|èpژq’ثŒأ•
پ@‚±‚ج“ْپi‚Q‚O‚O‚W”N‚QŒژ‚X“ْپj‚ج”ٍ’¹‚حپA’؟‚µ‚’‹‘O‚©‚ç‘هگل‚ھچ~‚葱‚’†‚جپuگ^‹|èpژq’ثŒأ•پvŒ»’nŒ©ٹw‰ï‚ئ‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پBˆ«“VŒَ‚ة‚à‚©‚©‚ي‚炸پA’©‚©‚瑽گ¨‚جچlŒأٹwƒtƒ@ƒ“‚ھ“rگط‚ê‚邱‚ئ‚ب‚–K‚ê‚ـ‚µ‚½پB
پ@چ~‚肵‚«‚éگل‚ج’†‚ةکب‚ق’·ژض‚ج—ٌ‚ًŒ©‚ؤ‚¢‚é‚ئپA‚ـ‚é‚إ‰f‰وپu”ھچb“cژRژ€‚جœfœrپv‚ً‘z‚ي‚¹‚éŒiٹد‚ً’و‚µپAˆَڈغ‚ةژc‚錩ٹw‰ï‚إ‚µ‚½پB پ@‚±‚جپuگ^‹|èpژq’ثŒأ•پv‚حپAڈ؛کa‚R‚V”N‚ة‚à“à•”‚ة‘حگد‚µ‚½“yچ»‚ھ”ہڈo‚³‚êژہ‘ھ’²چ¸‚ھچs‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپAچ،‰ٌ‚ح‚»‚ج‘S–e‰ً–¾‚ًچs‚¤‚½‚ك‚ة–¾“ْچپ‘؛‹³ˆçˆدˆُ‰ï‚ة‚و‚ء‚ؤ–{ٹi“I‚ب”Œ@’²چ¸‚ھچs‚ي‚ê‚ـ‚µ‚½پBŒ©ٹw‰ï‚إ‚ح‚±‚جŒأ•‚ج“à•”‚ً’ت‚蔲‚¯‚邱‚ئ‚ھڈo—ˆ‚ـ‚µ‚½‚ھپA‹گگخ‚ًپuژ‚؟‘—‚èپv‚ئŒؤ‚خ‚ê‚éƒhپ[ƒ€ڈَ‚ةگد‚فڈم‚°‚½Œأ•“à•”‚ج‹َٹش‚حپAگخ•‘‘نŒأ•‚ً‚à—½‚®‚ئژv‚ي‚ê‚éچL‚³‚ھ‚ ‚èپAگد‚فڈم‚°‚ç‚ꂽ‹گگخ‚ھچ،‚ة‚àگN“üژز‚ة”—‚ء‚ؤ—ˆ‚é‚و‚¤‚بˆذˆ³ٹ´‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پBŒ©ٹw‰ïŒم‚àŒأ•“à•”‚جŒِٹJ‚ھ—\’肳‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½‚ھپA•غ‘Sڈم‚ج–â‘è‚à‚ ‚èپA‚Q‚O‚O‚W”NŒ»چف‚ج‚ئ‚±‚ëŒِٹJ‚ج–عڈˆ‚ح—§‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚و‚¤‚إ‚·پB
پ@گ^‹|èpژq’ثŒأ•‚ھ‚ ‚éگ¼”ٍ’¹‚جٹLگپژRک[‚ة‚ح‚à‚¤ˆê‚آ‚جâuâƒژ®گخژ؛‚ً”؛‚¤èpژq’ث‚إ‚ ‚éپu—^ٹyèpژq’ثŒأ•پv‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپA‚±‚؟‚ç‚ح–¢‚¾–{ٹi“I‚ب”Œ@’²چ¸‚حچs‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚¹‚ٌپB |
 |

ٹ»‘نگص |
پ@‚±‚ج—^ٹyèpژq’ثŒأ•‚ج‚·‚®‹ك‚‚ة‚ ‚éپuƒJƒ“ƒWƒ‡Œأ•پv‚àâuâƒژ®گخژ؛‚ً”؛‚¤Œأ•‚إ‚·پBچإ‹ك‚ج”Œ@’²چ¸‚إ‘حگد“yچ»‚ًŒ@‚èڈo‚µ‚½‚ئ‚±‚ëپAگخژ؛‚ج’†‰›•”‚ة‘ه‰¤‰ئƒNƒ‰ƒX‚جگ¸چI‚بٹ»‘ن‚ج•”•ھ‚ھژc‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ھ”»–¾‚µ‚ـ‚µ‚½پB
èpژq’ثŒأ•‚ئ“¯—l‚ة“n—ˆŒnچ‹‘°‚جژٌ’·•و‚ج“ء’¥‚ً”ُ‚¦‚ب‚ھ‚çپAچ‚‹M‚ب••و‚ةŒ©‚ç‚ê‚é‹Hڈ‚بٹ»‘ن‚ًژ‚آ‚±‚ئ‚©‚çپA‚»‚ج”ي‘’ژز‚ھکb‘è‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB
|
پ@ڈم‹L‚ج‚±‚ê‚ç‚جŒأ•‚حپA‹گگخ‚ًƒhپ[ƒ€ڈَ‚ةگد‚فڈم‚°‚éâuâƒژ®گخژ؛‚ئŒؤ‚خ‚ê‚é“ءˆظ‚ب’z‘¢چH–@‚âپA•›‘’•i‚ةƒ~ƒjƒ`ƒ…ƒAگ†”ر‹ï‚ھ”؛‚¤ڈo“yˆâ•¨‚ج“ء’¥‚ب‚ا‚©‚çپA‚¢‚¸‚ê‚àپA‚±‚ج’nˆو‚ة’è’…‚µ‚½“n—ˆŒnچ‹‘°‚جژٌ’·•و‚ئچl‚¦‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚إ‚·پB
پ@‚ب‚¨پAپuŒ،‹چژq’ثŒأ•پv‚ئپuڈ¬’JŒأ•پv‚حپAگ¼”ٍ’¹‚جŒأ•‚ً‚ك‚®‚é—¼’خ‰ï‚ج‘و‚U‰ٌ’è—ل‰ï‚جچغ‚ة‰ٌ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@پuŒ،‹چژq’ثŒأ•پv‚حپA–ƒ•z‚ًژ½‚إŒإ‚ك‚½چ‚“x‚ب‹Z–@‚جڑٌمIٹ»‚ج”j•ذ‚ھڈo“y‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚âپA“ٌژ؛گخژ؛‚ج”ھٹpŒ`••و‚إ‚ ‚ء‚½‚±‚ئ‚©‚çپAٹشگlچcڈ—‚ئ‚ئ‚à‚ة–°‚éگؤ–¾“Vچc‚جچ‡‘’•و‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@“à•”‚ةٹW‚جٹJ‚¢‚½‰ئŒ^گخٹ»‚ھژc‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپuڈ¬’JŒأ•پv‚حپA•‹u‚ج••“y‚ھ‚·‚ء‚©‚èژ¸‚ي‚êپAٹLگپژR‚©‚çگL‚ر‚é”ِچھڈم‚ة‹گ‘ه‚بگخژ؛‚ھکIڈo‚µ‚ؤ‚¢‚é—¼‘³ژ®‰،Œٹگخژ؛‚جڈI––ٹْŒأ•‚إ‚·پB
پiژQچlپF–¾“ْچپ‘؛‚ج•¶‰»چà‚P‚Oپ@پuگ^‹|èpژq’ثŒأ•پvپj
پiژQچlپF”ٍ’¹—V–K•¶ŒةپE”ٍ’¹Œأوپ@پuگ^‹|èpژq’ثŒأ•Œ©ٹw‰ïپvپj
–â‚Vپ@پ@پ@ژں‚جژ›‚ج‚¤‚؟پA“ْ–{ڈ‘‹I‚ة–¼‘O‚ھŒ»‚ê‚ب‚¢‚ج‚ح‚ا‚ê‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚PپFwŒGژ›پ@پ@‚QپF‘هŒEژ›پ@پ@‚RپFŒyژ›پ@پ@‚SپFˆہ”{ژ›
پ@پu“ْ–{ڈ‘‹Iپvژé’¹Œ³”N‚WŒژ‚Q‚P“ْ‚ةپuwŒGژ›پEŒyژ›پE‘هŒEژ›‚ةگH••‚»‚ꂼ‚ê•SŒث‚ًپA‚R‚O”N‚ًŒہ‚èژ’‚ء‚½پv‚ئ‚ج‹Lچع‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپAˆہ”{ژ›‚ج‹Lچع‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‚ـ‚½پAwŒGژ›پE‘هŒEژ›پEŒyژ›‚ةٹض‚µ‚ؤ‚àپA‚±‚êˆبٹO‚ج‹Lژ–‚حپA“ْ–{ڈ‘‹I‚ة‚حŒ©‚ç‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB

ˆہ”{ژ› |
پ@ˆہ”{ژ›‚ح‚»‚جگص’n‚ھپAˆ¢”{ژR“c“¹‚ج“Œ’[پEچ÷ˆنژsˆ¢”{‚ة‚ ‚è‚ـ‚·پB‘nŒڑژز‚حپAچF“؟’©‚جچ¶‘هگbپEˆہ”{‘q’ٍ–ƒکC‚¾‚ئ‚³‚êپA“Œگ¼‚ة•ہ‚ش‹à“°پE“ƒ‚ً‰ٌکL‚ھˆح‚ق–@—²ژ›ژ®‰¾—•”z’u‚ھگ„’肳‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@ڈo“yˆâ•¨‚©‚çپA‚Vگ¢‹I’†چ ‚ة‚حŒڑ—§‚ة’…ژ肳‚ê‚ؤ‚¢‚½‚ئچl‚¦‚ç‚êپA‘q’ٍ–ƒکC‘nŒڑگà‚ً— •t‚¯‚éŒ`‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB |
پ@‚»‚جŒمپA“Œ‘هژ›‚ج––ژ›‚ئ‚ب‚èپu“Œ‘هژ›—vک^پv‚ة‚àپAˆہ”{ژ›‚ح•ت–¼پuگ’Œhژ›پvپA‘nŒڑژز‚حˆہ”{‘q’ٍ–ƒکC‚إ‚ ‚é‚ئ‹L‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
ٹ™‘qژ‘م‚ةˆع“]‚µپAŒ»ˆہ”{•¶ژê‰@‚ھ‚»‚جŒمگg‚¾‚ئ‚¢‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBˆہ”{•¶ژê‰@‹«“à‚ة‚حپA‚Vگ¢‹I’†چ ‚ة‘¢‚ç‚ꂽگ¸مk‚بگطگخ‘¢‚è‚ج•¶ژê‰@گ¼Œأ•‚âپA‚Vگ¢‹I‚ج‘O”¼‚ج脉¾ˆنپi‚ ‚©‚¢پjŒA‚ئ‚àŒؤ‚خ‚ê‚镶ژê‰@“ŒŒأ•‚ھ‚ ‚èپA‚±‚ê‚ç‚حˆہ”{ژپˆê‘°‚ج•و‚¾‚ئگ„’肳‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@‚P‚جwŒGژ›‚حپA–¾“ْچپ‘؛w‘O‚ة‚ ‚鉗”üˆ¢ژuگ_ژذ‚ج‹«“à‚ةگص’n‚ئ‚µ‚ؤژc‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‰—”üˆ¢ژuگ_ژذ‚حپA“Œٹ؟‚ج‘cپEˆ¢’qژgژهپi‚ ‚؟‚ج‚¨‚فپj‚ًچصگ_‚ئ‚µپAŒ³پXگ¼‘¤‚ج’ل’n‚ة‚ ‚ء‚½‚à‚ج‚ھپA–¾ژ،‚S‚O”N‚ةچ،‚جچ‚‘ن‚ض‚ئˆع“]‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پB
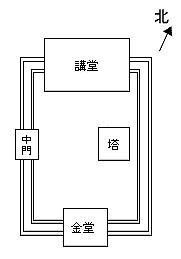
wŒGژ›‰¾—•”z’u |
پ@wŒGژ›‚حپAˆ¢’qژgژه‚©‚瑱‚“Œٹ؟ژپ‚جˆê’[‚ً‚ة‚ب‚¤wŒGژپ‚جژپژ›‚¾‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپAژé’¹Œ³”N‚جڈ‘‹I‚ج‹Lژ–ˆبٹO‚ة‚حگ³ژj‚ة‚à“oڈꂹ‚¸پAڈعچׂح•s–¾‚إ‚·پB
پ@wŒGژ›‰¾—•”z’uگ} پ@“ءˆظ‚ب‰¾—•”z’u‚حپA’nŒ`‚جگ§–ٌ‚ًژَ‚¯‚½‚à‚ج‚¾‚ئ‚¢‚¤گà‚à‚ ‚èپA‚Vگ¢‹IŒم”¼‚ة‹à“°پA‚Vگ¢‹I––‚ة“ƒ‚ئچu“°‚ھŒڑ‚ؤ‚ç‚ꂽ‚±‚ئ‚ھڈo“yˆâ•¨‚©‚çگ„’肳‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚±‚ج‚Qٹْ‚ة•ھ‚©‚ê‚éŒڑ—§‚ج”wŒi‚ة‚حپA‚U‚S‚T”N‚ج‘h‰نژپ–إ–SپA‚U‚V‚V”N‚ج“V•گ“Vچc‚©‚ç‚جژ¶گس‚ب‚اپA“Œٹ؟ژپ‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚جٹë‹@“Iڈَ‹µ‚ھ‚ ‚ء‚½‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·پBژپژ›Œڑ—§‚ً’ت‚µˆê‘°‚جŒ‹‘©‚ًŒإ‚كپAژگ¨‚ًڈو‚èگط‚낤‚ئ‚µ‚½‚ئ‚جŒ©•û‚à‚ ‚é‚و‚¤‚إ‚·پB‚ـ‚½پA”ٍ’¹ژ›‚ئچ“ژ—‚·‚éٹ¢‚جڈo“y‚à‚ ‚èپA‚»‚êˆب‘O‚ج‘Oگgˆâچ\‚ج‘¶چف‚àگ„‘ھ‚³‚ê‚ـ‚·پB |
پ@‚»‚جŒم‚جwŒGژ›‚حپA”Œ@’²چ¸‚©‚ç“ق—اژ‘م‚ـ‚إ‚حŒڑ•¨‚àˆغژ‚³‚êپA•½ˆہژ‘مŒم”¼‚ة‚حچu“°ٹî’d‚ج•âڈC‚âڈ\ژOڈd“ƒ‚جŒڑ—§‚ب‚ا‚ھچs‚ي‚ꂽ‚±‚ئ‚ھ‚ي‚©‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB’†گ¢‚ة‚حپAچu“°‚ھ“|‰َ‚µپA‚»‚جڈم‚ةڈ¬‚³‚ب‚¨“°‚ھŒڑ‚ؤ‚ç‚ꂽ‚ئگ„’è‚إ‚«‚é‚و‚¤‚إ‚·پB
پiژQچlپF–{‹ڈگé’·پ@پuگ›ٹ}“ْ‹L‰؛‚جٹھپvپ@پj
پiژQچlپFwŒGژ›گصپ@پj
پ@‚Q‚ج‘هŒEژ›‚حپAٹ€Œ´ژs‘ه‹v•غ’¬‚ة‚ ‚éچ‘Œ¹ژ›‚ھ–@“”‚ً“`‚¦‚é‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

چ‘Œ¹ژ›•t‹ك |
پ@‘هŒEژ›‚à“ْ–{ڈ‘‹I‚جژé’¹Œ³”N‚ج‹Lژ–‚ة‚»‚ج–¼‚ھ‚ف‚¦‚邾‚¯‚إپA‰¾—•”z’u‚à–¾‚ç‚©‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB“ƒگS‘b‚ئ“`‚¦‚ç‚ê‚é‘bگخ‚ھچ‘Œ¹ژ›‹ك‚‚ة’u‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
‚±‚ج‘bگخ‚ج“ى‘¤‚ھ”Œ@’²چ¸‚³‚êپAŒ@—§’ŒŒٹ‚ب‚ا‚ھŒںڈo‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA‘هŒEژ›‚ةٹضکA‚·‚é‚à‚ج‚©‚ا‚¤‚©‚ج’f’è‚ح‚إ‚«‚ب‚¢‚و‚¤‚إ‚·پB |
پ@ڈo“y‚µ‚ؤ‚¢‚錬ٹ¢‚ةپAŒyژ›ژ®‚ةچ“ژ—‚·‚é‚à‚جپAژR“cژ›ژ®‚ةچ“ژ—‚·‚é‚à‚ج‚ب‚ا‚ھ‚ ‚èپA‚±‚ê‚ç‚ھ‘هŒEژ›‘nŒڑ‚ةژg—p‚³‚ꂽ‚ئگ„’è‚·‚ê‚خپA‚Vگ¢‹I’†چ ‚ة‚ح‰½‚ç‚©‚ج“°‰F‚ھŒڑ—§‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½‰آ”\گ«‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB

Œy‰“–]
پiŒـڈً–ىٹغژRŒأ•‚و‚è–k‚ً–]‚قپj |
پ@‚R‚جŒyژ›‚حپAٹ€Œ´ژs‘هŒy’¬پEŒـڈً–ىپiŒ©گ£پjٹغژRŒأ•‚ج— ژèپi–k‘¤پj‚جŒ»چف‚ج–@—ضژ›ژü•س‚ة‚ ‚ء‚½‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBژ›ˆو‚حپA–kŒہ‚ئژv‚ي‚ê‚é’Œ—ٌ‚جŒںڈo‚âژü•س’nŒ`‚ئ‚جٹش‚ةگ”ƒپپ[ƒgƒ‹‚جچ‚’لچ·‚ھ”F‚ك‚ç‚ê‚é“_‚ب‚ا‚©‚çپA“ى–k‚ح‚P‚S‚O‚چˆبڈمپA“Œگ¼‚ح‚U‚T‚چ’ِ‚جژ›ˆو‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ئگ„’肳‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚±‚ج•س‚è‚حپA‰؛‚آ“¹‚ئژR“c“¹‚جŒًچ·‚·‚é•س‚è‚إپA•t‹ك‚حپuŒy‚ج‚؟‚ـ‚½پv‚ئŒؤ‚خ‚êپAŒأ‘م‚ة‚ح“ِ‚ي‚ء‚½’nˆو‚إ‚ ‚ء‚½‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚ھپAŒyژ›‚à‚ـ‚½پAڈم‹L‚ج‚Qژ›‚ئ“¯‚¶‚“ْ–{ڈ‘‹I‚جژé’¹Œ³”N‚ج‹Lژ–‚ة‚»‚ج–¼‚ھ‚ف‚¦‚邾‚¯‚إپA‘nŒڑ‚جڈعچׂح•s–¾‚إ‚·پB
پ@‰ê—¯‘هگbŒ؛—‘nŒڑگàپi–@—ضژ›ˆؤ“à”آپj‚â“Œٹ؟‚ةŒyٹُگ،‚ب‚ا‚ج–¼‘O‚ھŒ©‚¦‚邱‚ئ‚©‚çپA“n—ˆŒn‚جŒyژپ‚جژپژ›‚إ‚ ‚ء‚½‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBŒyژ›ژ®‚ئŒؤ‚خ‚ê‚é“ءˆظ‚ب•¶—l‚جڈo“yٹ¢‚©‚çپA‚Vگ¢‹I’†چ ‚ة‚ح‚ب‚ٌ‚ç‚©‚ج“°‰F‚ھŒڑ—§‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½‚ئگ„’肳‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚ـ‚½پA•½ˆہژ‘م‚ة‚حپA“،Œ´“¹’·‚ھڈh‚ئ‚µ‚ؤ—ک—p‚µ‚ؤ‚¢‚éژ–‚©‚çپA‚ ‚é’ِ“x‚ج‹K–ح‚ً•غ‚ء‚ؤŒمگ¢‚ـ‚إ‘¶‘±‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·پBپiژQچlپFŒyژ›گصپj
پ@wŒGژ›پE‘هŒEژ›پEŒyژ›‚حپA‚ا‚ê‚à“n—ˆŒnژپ‘°‚جژپژ›‚¾‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚»‚جچھ‹’‚ح—lپX‚إ‚·‚ھپAژé’¹Œ³”N‚جگH••‚ج‹Lژ–‚ة•ہ—ٌ‚µ‚ؤ–¼‚ھڈم‚°‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ھ‚©‚ب‚è‚جٹ„چ‡‚ًگè‚ك‚ؤ‚¢‚é‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB‚ـ‚½پAٹ™‘qٹْ‚ـ‚إٹmژہ‚ة‘¶‘±‚µپAŒ»چف‚à–@“”‚ًŒp‚®ژ›‰@‚ھ‚ ‚é‚ة‚à‚©‚©‚ي‚炸پA‰½Œجˆہ”{ژ›‚ھگ³ژj‚ة“oڈꂵ‚ب‚¢‚ج‚©‚ًچl‚¦‚ؤ‚ف‚é‚ج‚à–ت”’‚¢‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB
–â‚Wپ@پ@پ@گpگ\‚ج—گ‚إپA‹كچ]•û‚ة‚آ‚«‚ب‚ھ‚ç‚àپAŒم‚ة‹–‚³‚ê‚ؤ‘هگb‚ة‚ـ‚إڈoگ¢‚µ‚½‚ج‚ح’N‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚PپF’†گb‹àپ@پ@‚QپF‘h‰نگشŒZپ@پ@‚RپF•¨•”–ƒکCپ@پ@‚SپF‘½ژ،”ن“ˆ
پ@•¨•”–ƒکC‚حپAگpگ\‚ج—گ‚ة‚¨‚¢‚ؤ‹كچ]’©‚ج‘هڈ«پE‘ه—Fچcژq‚ةچإŒم‚ـ‚إ•t‚«ڈ]‚ء‚½ˆêگl‚إ‚·‚ھپA‚ب‚؛‚©—گŒمپAچك‚ة‚ح–â‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚¹‚ٌپB‚±‚ê‚حپA’‰گ½گS‚ً”ƒ‚ي‚ꂽ‚ئ‚àپA“V•گ‘¤‚ة‹ڈ‚½“¯‘°پi–pˆنکA—YŒNپEƒGƒmƒCƒmƒ€ƒ‰ƒWƒIƒLƒ~پj‚جٹˆ–ô‚ج‚¨‰A‚¾‚ئ‚àŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚إ‚·‚ھپAگ^‘ٹ‚ح“ن‚إ‚·پB‚»‚جŒمپA“V•گ‚T”Nپi‚U‚V‚Uپj‚ةگV—…‚ض‘هژg‚ئ‚µ‚ؤ•‹‚«پA“V•گ‘’‘—‚جچغ‚ة‚ح–@ٹ¯‚ة‚آ‚¢‚ؤوn‚ً‚µپAژ“‚R”Nپi‚U‚W‚Xپj‚ة‚حپA’}ژ‡‚ة”hŒ‚³‚êپAژ“‚S”Nپi‚U‚X‚Oپj‚ج“Vچc‘¦ˆت‚جچغ‚ة‚حپA‘هڈ‚‚ً—§‚ؤ‚é–ً‚ً‰ت‚½‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚»‚جŒمپA•¶•گ’©‚ة‰E‘هگbپAŒ³–¾’©‚ةچ¶‘هگb‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·‚ھپA•½ڈé‘J“s‚جگـ‚è‚ة‚حپAچ‚—î‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚à‚ ‚ء‚½‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤پA‹Œ“s‚ج—¯ژç–ً‚ئ‚µ‚ؤ“،Œ´‚ةژc‚è‚ـ‚·پB
پ@•¨•”–ƒکC‚حپA“V•گ‚P‚R”Nپi‚U‚W‚Sپj‚ة‘¼‚ج‚T‚Qژپ‚ئ‚ئ‚à‚ةپu’©گbپv‚ًژ’‚èپA‚»‚جŒم‚ةژپ–¼‚ًپuگخڈمپv‚ة•د‚¦‚½‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚µ‚½‚ھ‚ء‚ؤپA“ْ–{ڈ‘‹I‚ة“oڈê‚·‚éپu•¨•”کA–ƒکCپv‚ئپuگخڈم’©گb–ƒکCپv‚حپA“¯ˆêگl•¨‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پBپiژQچlژ‘—؟پF•¨•”ژپŒnگ}پj
پ@گpگ\‚ج—گŒم‚ج‚WŒژ‚Q‚T“ْ‚جڈˆ‹ِ‚إپAڈdچك‚Wگl‚ھژ€چك‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@‚P‚ج’†گb‹àپi‹كچ]’©‰E‘هگbپj‚حژhژE‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@‚Q‚ج‘h‰نگشŒZپi‹كچ]’©چ¶‘هگbپj‚حپAژqپE‘·‚ئ‚à‚ا‚à—¬چك‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·پB
پ@‚S‚ج‘½–è”ن“ˆ‚حپAچ¶‰E‘هگb‚ة”C‚¶‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپAگpگ\‚ج—گ‚جگـ‚è‚ة‹كچ]•û‚ة‚آ‚¢‚½‚ئ‚ج‹Lچع‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‘½–è”ن“ˆ‚حپAپu‘½–è”نگ^گl“ˆپv‚ئ‚àڈ‘‚©‚ê‚ـ‚·پBپuگ^گlپv‚ئ‚حپA“V•گ‚P‚R”N‚ة’è‚ك‚ç‚ꂽ”ھگF‚جگ©‚ج‚¤‚؟‚جچإچ‚ˆت‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پBپi“ˆ‚حپAگ鉻“Vچc‚ج’¼Œn‚جژq‘·پj
پ@‚ـ‚½پAژپ–¼‚جپu‚½‚¶‚ذپv‚حپAپu’O”نپv‚ئ‚àڈ‘‚©‚êپA“ْ–{ڈ‘‹I‚حژه‚ة‚±‚ج•\‹L‚ًژو‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA•¶•گ“VچcˆبŒم‚جگ³ژj‚إ‚ ‚鑱“ْ–{‹I‚إ‚حپAپu‘½–è”نگ^گl“ˆپv‚ئڈ‘‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@پu’O”نپv‚ج•\‹L‚حپA”ق‚ç‚ھ‰ح“àچ‘’O”نŒS‚ً–{‹’’n‚ئ‚·‚éژپ‘°‚إ‚ ‚ء‚½‚±‚ئ‚ھ——R‚ئ‚àچl‚¦‚ç‚ê‚ـ‚·پB“ْ–{ڈ‘‹I‚ئ‘±“ْ–{‹I‚ةŒ©‚¦‚邱‚ê‚ç‚جˆل‚¢‚حپA‚»‚ꂼ‚ê‚جگ¬—§ژٹْ‚ة‚¨‚¯‚镶ژڑ‚ض‚ج”Fژ¯‚جˆل‚¢‚ة‚و‚é‚à‚ج‚¾‚ئژv‚¦‚ـ‚·پBپiژQچlژ‘—؟پF•¨•”ژپŒnگ}پj
–â‚Xپ@پ@پ@’·‰®‰¤‚ھ•ƒپEچ‚ژsچcژq‚ج‹ں—{‚ج‚½‚ك‚ة‘¢‚ء‚½‚ئچl‚¦‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éژ›‚ح‚ا‚ê‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚PپFگآ–ط”pژ›پ@پ@‚QپFچ‚ژs‘هژ›پ@پ@‚RپF‹»‘Pژ›پ@پ@‚SپF’è—رژ›
 |
پ@گآ–ط”pژ›گص‚حپA“ق—اŒ§چ÷ˆنژs‹´–{‚ة‚ ‚è‚ـ‚·پBڈo“yٹ¢‚ج’†‚ةپA‰ھژ›‚ج‘nŒڑٹْ‚ةژg—p‚³‚ꂽٹ¢‚ئچ“ژ—‚·‚é‚à‚ج‚ھ”F‚ك‚ç‚ê‚邱‚ئ‚©‚çپA’x‚‚ئ‚à‚Vگ¢‹I––‚©‚ç‚Wگ¢‹Iڈ‰“ھ‚ة‚حŒڑ—§‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@‚ـ‚½پAڈo“y‚µ‚½Œ¬•½ٹ¢‚ج’†‚ةپAپu‰„ٹىکZ”N’d‰zچ‚ٹK–خگ¶پv‚ئٹ¢“––ت‚ة‹tژڑ‚ج–ء•¶‚ًژ‚آ‚à‚ج‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚±‚ê‚ة‚و‚艄ٹى‚U”Nپi‚X‚O‚Uپj“–ژپAگآ–ط”pژ›‚ئچ‚ٹKژپ‚ة‰½‚ç‚©‚جŒq‚ھ‚è‚ھ‚ ‚ء‚½‚ئ‘z’è‚إ‚«‚ـ‚·پBچ‚ٹKژپ‚حپAچ‚ژsچcژq‚ئŒن–¼•”چcڈ—‚جژq‚إ‚ ‚é’·‰®‰¤‚ً‘c‚ئ‚·‚éˆê‘°‚ھپA•½ˆہژ‘مپiڈ³کa‚P‚P”NپE‚W‚S‚Sپj‚ةگbگذچ~‰؛‚µ‚½گـ‚è‚ةژ’‚ء‚½گ©‚إ‚·پB
پ@ڈo“yٹ¢‚ة‚و‚é‘nŒڑ”N‘م‚ئچ‚ٹKژپ‚ئ‚جٹض‚ي‚è‚ب‚ا‚جگ„’è‚©‚çپAگآ–ط”pژ›‚ھژ“‚P‚O”Nپi‚U‚X‚Uپj‚ة–v‚µ‚½چ‚ژsچcژq‚ج‹ں—{‚جˆ×‚ة’·‰®‰¤پi‚U‚W‚Sپ`‚V‚Q‚Xپj‚ھŒڑ—§‚µ‚½‚ئ‚àچl‚¦‚ç‚ê‚é‚و‚¤‚إ‚·پB
پiژQچlژ‘—؟پF”ٍ’¹ژ‘م“Vچc‰ئŒnگ} پj
پ@‚Q‚جچ‚ژs‘هژ›‚حپA•Sچد‘هژ›‚ً“V•گ‚Q”N‚ةچ‚ژsŒS‚ةˆع‚µ–¼‚ً‰ü‚ك‚½‚ئ‚³‚ê‚éژ›‚ة‚ب‚è‚ـ‚·‚ج‚إپA‘nŒڑ”N‘م‚ھŒأ‚‚ب‚èپAگف–â‚ة‚حچ‡‚¢‚ـ‚¹‚ٌپB
پ@‚R‚ج‹»‘Pژ›‚حپAچپ‹ïژR‚ج“ىک[‚ة‚ ‚éژ›‚إپA‘هˆہژ›‚ج“¹ژœ—¥ژt‚ھٹJ‚¢‚½چپ‹vژRژ›پiچپژRژ›پj‚جŒمگg‚ئŒ¾‚ي‚ê‚ـ‚·‚ھپAژ›ˆو‚©‚ç‚ح–{–ٍژtژ›پE“،Œ´‹{پE‰ھژ›‚ب‚ا‚ج—lژ®‚جŒأٹ¢‚ھڈo“y‚µپA‘nŒڑ‚ح“ق—اژ‘مˆب‘O‚ة‘k‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB•t‹ك‚©‚ç‚حپA‘هŒ^–x—§’ŒŒڑ•¨‚P“ڈ‚â‚»‚ê‚ًˆح‚ق•»پA’GŒٹژ®ڈZ‹ڈ‚ب‚ا‚àŒ©‚آ‚©‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپAڈعچׂح•s–¾‚ج‚و‚¤‚إ‚·پB
پ@‚S‚ج’è—رژ›‚حپA‘nŒڑ‚جڈعچׂح•s–¾‚ب‚ھ‚ç‚àگ¹“؟‘¾ژqŒڑ—§‚S‚Uƒ–ژ›‚ةگ”‚¦‚ç‚êپAڈo“yٹ¢‚©‚ç‚جگ„’è‘nŒڑ”N‘م‚حپA’x‚‚ئ‚à‚Vگ¢‹Iڈ‰“ھ‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ج‚إپAگف–â‚جژ‘م‚ة‚حچ‡‚¢‚ـ‚¹‚ٌپB
–â‚P‚Oپ@پ@ژR“cژ›‚ح•¶Œ£ژ‘—؟‚©‚ç‘¢‰c‰ك’ِ‚ھ’m‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA‚»‚جژ‘—؟‚ئ‚ح‚ا‚ê‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚PپFڈم‹{گ¹“؟–@‰¤’éگà— ڈ‘پ@پ@ پ@‚QپF“ْ–{چ‘Œ»•ٌ‘Pˆ«—ىˆظ‹Lپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚RپF‹»•ںژ›‰¾—••ہ—¬‹Lژ‘چà’ پ@پ@‚SپF•}ŒK—ھ‹L

‘هکaپEژR“cژ›گصپi“ى‚©‚çپj |
پ@ڈم‹{گ¹“؟–@‰¤’éگà‚حپA‚Wگ¢‹Iپ`‚Xگ¢‹I‚ةگ¬—§‚µ‚½‚ئŒ¾‚ي‚ê‚é—ًژjڈ‘‚إپAژه‚ةگ¹“؟‘¾ژqٹضکA‚جŒn•ˆ‚ب‚ا‚ھ‹Lچع‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚±‚ج— ڈ‘پi–{•¶— –ت‚ة•ت‚ج•Mگصپj‚ةژR“cژ›‚ج‘¢‰c‰ك’ِ‚ھ‹L‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@‚Q‚جپu“ْ–{چ‘Œ»•ٌ‘Pˆ«—ىˆظ‹Lپv‚حپAپu“ْ–{—ىˆظ‹Lپv‚ئˆê”ت‚ةŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚جگ³ژ®–¼ڈج‚إ‚·پBڈمپE’†پE‰؛‚ج‚Rٹھ‚©‚ç‚ب‚é‚Xگ¢‹Iپi•½ˆہژ‘مپj‚ة•ز‚ـ‚ꂽ•§‹³گàکbڈW‚إ‚·پB
پ@‚R‚جپu‹»•ںژ›‰¾—••ہ—¬‹Lژ‘چà’ پv‚حپA•¶ژڑ’ت‚è‹»•ںژ›‚جŒڑ—§ژں‘و‚âژ›“à‚ة”[‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é•َ•¨‚â”ُ•i‚ب‚ا‚ھ‹Lک^‚³‚ꂽ‚à‚ج‚إ‚·پB
پ@‚S‚جپu•}ŒK—ھ‹Lپv‚حپA‚P‚Oگ¢‹Iپi•½ˆہژ‘مپj‚ة‘mچc‰~‚ة‚و‚ء‚ؤ•زژ[‚³‚ꂽ•ز”N‘ج‚ج—ًژjڈ‘‚إ‚·پB
–â‚P‚Pپ@پ@Œن@ژgڈ¬–ى–…ژq‚ھ‚µ‚½‘هژ¸”s‚ئ‚ح‚ا‚ê‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚PپFن@ژg‚ً”ٍ’¹‚ةˆؤ“à‚·‚éچغ‚ج“¹‚ًٹشˆل‚¦‚½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚QپFن@’é‚جچ‘ڈ‘‚ً•´ژ¸‚µ‚½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚RپFن@’é‚©‚ç“Vچc‚ة‘—‚ç‚ꂽ‹àˆَ‚ً‚ب‚‚µ‚½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚SپF’}ژ‡‚ةڈم—¤‚µ‚½چغپAن@ژg‚ئ‚ح‚®‚ꂽ
پ@گ„Œأ‚P‚T”N‚VŒژ‚ةن@‚ض“n‚ء‚½ڈ¬–ى–…ژq‚حپA—‚”N‚SŒژ‚ة‹A’©‚µ‚ـ‚·پBن@ژg‚جهèگ¢گ´‚ç‚ئ‹¤‚ة’}ژ‡‚ًŒo‚ؤپA‚UŒژ‚ة‚ح“ï”g’أ‚ة“ü‚è‚ـ‚·پB“ْ–{ڈ‘‹I‚ج‚»‚جژ‚ج‹Lژ–‚ةپuژ„‚ھ‹Aٹز‚جژپAàŒ’é‚ھڈ‘‚ًژ„‚ةژِ‚¯‚ـ‚µ‚½پB‚ئ‚±‚ë‚ھ•Sچدچ‘‚ً’ت‚éژپA•Sچدگl‚ھ‚±‚ê‚ً—©‚ك‚ئ‚è‚ـ‚µ‚½‚½‚ك‚ةپA‚±‚ê‚ً‚¨“ح‚¯‚·‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚¹‚ٌپv‚ئ‚ ‚è‚ـ‚·پBژgژز‚ئ‚µ‚ؤ‚ج”C–±‚ً‰ت‚½‚³‚ب‚©‚ء‚½‚ئ‚µ‚ؤپA—¬ŒY‚ةڈˆ‚·‚ׂ«‚¾‚ئ‚¢‚¤ŒQگb‚جگ؛‚ةپA“Vچc‚ج‚¨™é‚ك‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½پB
پ@‚±‚ê‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA—lپX‚ب‰¯‘ھ‚àگ¶‚ـ‚ê‚ـ‚·‚ھپAڈ‘‹I‚ح‚½‚¾ٹبŒ‰‚ةڈ‘‚«—¯‚ك‚ؤ‚¢‚é‚ة‰ك‚¬‚ب‚¢‚و‚¤‚ةژv‚¦‚ـ‚·پB
–â‚P‚Qپ@پ@ژں‚جژ›–¼‚ئ–@چ†‚ج‘g‚فچ‡‚ي‚¹‚إٹشˆل‚ء‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚ح‚ا‚ê‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚PپF”ٍ’¹ژ›-–@‹»ژ›پ@پ@‚QپF–L‰Yژ›-Œڑ‹»ژ›
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚RپFژR“cژ›-“¹‹»ژ›پ@پ@‚SپF‹kژ›-•ى’ٌژ›
پ@ژR“cژ›‚ج–@چ†‚حڈٍ“yژ›پB“¹‹»ژ›‚حwŒGژ›‚ج–@چ†‚إ‚·پB
پ@–{‹ڈگé’·‚جگ›ٹ}“ْ‹L‚ج‹g–ى‚©‚ç”ٍ’¹‚ض“ü‚é•س‚è‚جکb‚ةپAپu‚¾‚¤‚‚ي‚¤‚¶پv‚ئŒ¾‚¤ژ›‚ھڈo‚ؤ‚«‚ـ‚·پB‚±‚جپu‚¾‚¤‚‚ي‚¤‚¶پv‚ةژٹ‚é‚ـ‚إ‚ج•`ژت‚ھپA‚ـ‚³‚ةŒ»چف‚جwŒGژ›گص•t‹ك‚ج—lژq‚ةژ—‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@گé’·‚ھپAژ›‚جˆء‚ةڈZ‚ـ‚¤–@ژt‚ةپu‚±‚±‚ح‚ا‚¤‚¢‚¤ژ›‚©پv‚ئگq‚ث‚é‚ج‚إ‚·‚ھپAپuگ鉻“Vچc‚ج‹{‚جگص‚ة—§”h‚بژ›‚ھ‚ ‚ء‚½‚ھ”R‚¦‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پv‚ئŒ¾‚¤ˆبٹO‰½‚à•ھ‚©‚炸پA“y’n‚جگl‚ة•·‚¢‚ؤ‚â‚ء‚ئژ›–¼‚ھپu“¹‚جŒُپv‚ئڈ‘‚‚ئ‹³‚¦‚ç‚ê‚ـ‚·پB
پ@–â‚V‚ج‰ًگà‚ة‚àڈ‘‚«‚ـ‚µ‚½‚ئ‚¨‚èپAwŒGژ›‚إ‚ح’†گ¢‚ة“|‰َ‚µ‚½چu“°گص‚ج‘bگخ‚ً—ک—p‚µ‚ؤ‘¢‚ç‚ꂽ•§“°پiژOٹشژl•ûپj‚ھپA’†‰›–k‚و‚è‚ة‘¶چف‚µ‚½‚±‚ئ‚ھ•ھ‚©‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

wŒGژ›چu“°گص |
پ@گé’·‚ھ–¾کa‚X”N(‚P‚V‚V‚Qپj‚RŒژ‚P‚O“ْ‚ةŒ©‚½پu‚¾‚¤‚‚ي‚¤‚¶پv‚جپu‚©‚è‚»‚ك‚ب‚é‚¢‚ظ‚èپv‚حپA‚±‚جچu“°گص‚ة—§‚ء‚ؤ‚¢‚½‚Rٹشژl•û‚جڈ¬‚³‚ب•§“°‚جگ¬‚ê‚ج‰ت‚ؤ‚¾‚ء‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB‘m‚ئ‚àŒؤ‚ׂب‚¢‚و‚¤‚ب–@ژt‚ھڈZ‚ـ‚¤ˆء‚ھپAwŒGژ›‚جچ]Œثژ‘م‚جژp‚¾‚ء‚½‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB |
پ@‚ـ‚½پAپu‘ه“ْ–{’n–¼ژ«ڈ‘پi‹g“c“ŒŒق’کپE‚P‚X‚O‚V”Nٹ§چsپjپv‚ة‚حپAپu‰—”üˆ¢ژuپsƒIƒ~ƒAƒVپtگ_ژذپ@‰„ٹىژ®‚ة—ٌ‚µپAچ،w‘O‚ةچف‚èپA‘mژة‚ً’u‚«”V‚ًژç‚éپA“¹‹»ژ›‚ئH‚سپB‰—”üˆ¢ژu‚حژj‚ةژgژهˆ¢’q‚ئ‰]‚س‚ة‚ ‚½‚éپA‘¦w‘Oٹُگ،‚ج‘cگ_‚ب‚èپBپv‚ئ‚à‚ ‚è‚ـ‚·پB
پ@“¹Œُژ›‚ئ“¹‹»ژ›‚جژ›–¼‚جˆل‚¢‚حپAگé’·‚ھگ›ٹ}“ْ‹L‚إŒê‚ء‚½‚ئ‚±‚ë‚جپu‚©‚½‚è‚ذ‚ھ‚ك‚½‚éژ–پvپu–”‚«پT‚½‚ھ‚ض‚½‚é‚س‚µپv‚ب‚ا‚ة‚ ‚½‚èپAŒû“`‚³‚ê‚邤‚؟‚ة•د‰»‚µ‚ؤ‚¢‚ء‚½‚à‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB
پ@پiژQچlژ‘—؟پF–{‹ڈگé’·پ@پuگ›ٹ}“ْ‹L‰؛‚جٹھپvپj
–â‚P‚Rپ@پ@”ٍ’¹ژ›‚ج“ƒگS‘b‚جڈم‚ةپAژة—ک‚ئ‹¤‚ة’u‚©‚ꂽ‘‘Œµ‹ï‚ةٹـ‚ـ‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ج‚ح‚ا‚ê
‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚PپFŒù‹تپ@پ@پ@‚QپFkچbپ@پ@پ@‚RپF”n—éپ@پ@پ@‚SپF“؛‹¾
 |
پ@”ٍ’¹ژ›‚ج“ƒ‚حپA‚P‚P‚X‚U”Nپiٹ™‘qژ‘مپj‚ة—ژ—‹‚ة‚و‚èڈؤژ¸‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB—‚”NگS‘b–„”[•¨‚حپAŒ@‚è‹N‚±‚³‚êچؤ–„”[‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
‚±‚جژ‚جŒ@‚èژc‚µ‚ئژv‚ي‚ê‚éŒù‹تپA‹àٹآپA‹à“؛گ»‘إڈo‚µ‹à‹ïپA‹à‹â‰„”آپAkچbپA”n‹ï‚ئŒ©‚ç‚ê‚éگآ“؛گ»—é‚âژضچsڈً“Sٹي‚ب‚ا‚حپA‚P‚X‚T‚V”N‚ج”Œ@’²چ¸‚إ”Œ©‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA“؛‹¾‚ح”Œ©‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚¹‚ٌپBپi‚±‚ê‚çڈo“y•i‚حپA”ٍ’¹ژ‘—؟ٹظ‚جڈيگف“Wژ¦‚إ‚²——‚ة‚ب‚ê‚ـ‚·پB‚ـ‚½پAˆہ‹ڈ‰@‹«“à‚ة‚حپA“ƒگS‘b‚جˆت’u‚ة•W‚ھ—§‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپj |
پ@”n‹ï‚â•گ‹ï‚ب‚اŒأ•‚ج•›‘’•i‚ج‚و‚¤‚ب“ƒ–„”[•¨پiژة—ک‘‘Œµ‹ïپj‚ھٹm”F‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚حپA”ٍ’¹’nˆو‚إ‚ح”ٍ’¹ژ›‚¾‚¯‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پBپi•§‹ïˆبٹO‚جژة—ک‘‘Œµ‹ï‚جڈo“y‚حپAژl“V‰¤ژ›‚â’è—رژ›‚إ‚ح‹àٹآپA–@—²ژ›‚إ‚حٹCڈb•’“¸‹¾‚ب‚ا‚ھ‚ف‚ç‚ê‚ـ‚·پBپj
پiژQچlپF‘و‚P‚O‰ٌ’è—ل‰ïژ––±‹اˆُ”•\ƒŒƒ|پ[ƒgپ@گS‘b‚ئ–„”[•¨‚ج‚¨کbپj
پiژQچlپF”ٍ’¹Œں’è‰ًگàڈWپEچlŒأ•زپ@پj
پiژQچlپFپ@”ٍ’¹ژ›’TŒںپj
–â‚P‚Sپ@پ@پ@‹Tگخ‚حپA‚ ‚éژjگص‚ج‚آ‚¯‚½‚è‚ئ‚µ‚ؤژjگصژw’肳‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA‚»‚جژjگص‚ئ‚ح‚ا‚ê‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚PپFچ‚ڈ¼’ثŒأ•پ@پ@‚QپFگىŒ´ژ›پ@پ@‚RپFگخ•‘‘نŒأ•پ@پ@‚SپF‹kژ›
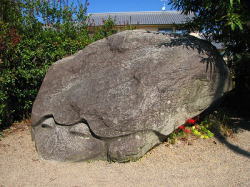 |
پ@‹Tگخ‚حپA‹kژ›‚ج‚ظ‚عگ^گ¼‚ة‚ ‚邱‚ئ‚©‚çپA‹kژ›‚ئˆê‘ج‚ج‚à‚ج‚ئژv‚ي‚ê‚ھ‚؟‚إ‚·‚ھپAژہچغ‚ة‚حگىŒ´ژ›گص‚جˆê•”‚ئ‚µ‚ؤژjگصژw’è‚ًژَ‚¯‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@Œ»چف‚حپAŒ§“¹‚ة‚و‚ء‚ؤ“ى–k‚ة—£‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‹Tگخ‚ئگىŒ´ژ›‚إ‚·‚ھپA‘هژڑ‚ج‹«ٹEگü‚ھ‹Tگخ•t‹ك‚ج—¢“¹‚ة‰ˆ‚ء‚ؤگف’肳‚ê‚ؤ‚¢‚邽‚ك‚ةپA‹Tگخ‚جڈٹچف’n‚حپu‘هژڑگىŒ´پv‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB |
پ@‰i‹v‚S”N(‚P‚P‚P‚U)‚جچO•ںژ›ژ›—ج‚جگ\گ؟•¶ڈ‘‚ج’†‚ةپuژڑ‹Tگخٹ_“àپv‚ئ‚ج•\‹L‚ھ‚ ‚èپA•½ˆہژ‘مپA‹Tگخ‚ج•t‹ك‚حگىŒ´ژ›‚جژ›—ج‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½‚±‚ئ‚ھ‚ي‚©‚è‚ـ‚·پBڈ؛کa‚R‚T”N‚ج“ق—اچ‘—§•¶‰»چàŒ¤‹†ڈٹ‚ة‚و‚锌@’²چ¸‚جچغپA‚±‚ج‰i‹v‚S”N‚جژj—؟‚ً‚à‚ئ‚ة‹Tگخ‚ھگىŒ´ژ›‚جژ›ˆو‹«ٹEگخ‚¾‚ئچl‚¦‚ç‚ꂽٹضŒW‚إپAگىŒ´ژ›‚جˆê•”‚ئ‚µ‚ؤژjگصژw’è‚ًژَ‚¯‚½‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·پB
پ@‚±‚ج‘¼پA‹Tگخ‚ھ‰½‚إ‚ ‚é‚©—lپX‚بگà‚ھ‚ ‚é‚ج‚إپAˆê•”‚²ڈذ‰î‚µ‚ؤ‚¨‚«‚ـ‚·پB
پ@‹kژ›‚جژ›ˆو‹«ٹE‚ًژ¦‚·•WگخگàپA’nŒ`“I‚ة”ٍ’¹‹ˆو‚ًژ¦‚·•WگخگàپA‰ح“à–ى’†ژ›‚ج‹T‚جگüچڈ‚ھ‚ ‚é‘bگخ‚ة—قژ—‚·‚éگخگàپA‹Tوéپi‚«‚سپjگà‚ب‚ا‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پBپi‹Tوه‚حپA‹T‚جŒ`‚ً‚µ‚ؤ”è“™‚ج‘نچہ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚ًŒ¾‚¢‚ـ‚·پB‚±‚ج‹T‚حپA—´‚جژq‚ًژ¦‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚àŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‹T‚ھ“V’n‚ًژx‚¦‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚·‚éگ_کb‚حپAƒCƒ“ƒh‚â’†چ‘‚ة‚ف‚¦پA‹Tوه‚ح‚»‚جڈم‚ةŒڑ‚آ‚à‚ج‚ةŒ ˆذ‚ًژ‚½‚¹‚邽‚ك‚ة—p‚¢‚ç‚ꂽ‚و‚¤‚إپA’†چ‘‚إ‚ح‚»‚جژg—p‚ةŒµ‚µ‚¢گg•ھگ§Œہ‚ھ‚ ‚ء‚½‚و‚¤‚إ‚·پBپj
پiژQچlپF”ٍ’¹‚جگخ‘¢•¨پ@‹Tگخپj
–â‚P‚Tپ@پ@پ@”ٍ’¹ژ›‘¢‰c‚جچغ‚ة•Sچد‚©‚çٹ¢چHگl‚ھ“n—ˆ‚µ‚ـ‚µ‚½‚ھپA‚»‚جگlگ”‚ح“ْ–{ڈ‘‹I‚ة‚و‚é‚ئ‰½گl‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚PپF‚Pگlپ@پ@پ@‚QپF‚Qگlپ@پ@پ@‚RپF‚Rگlپ@پ@پ@‚SپF‚Sگl
پ@گ’ڈs“VچcŒ³”Nپi‚T‚W‚Wپj‚ة•Sچد‚©‚畧ژة—ک‚ھŒ£ڈم‚³‚êپA‚»‚ê‚ة‘±‚¢‚ؤ‘m‚ئ”ژژmپEچHپi‚½‚‚فپj‚ئŒؤ‚خ‚ê‚é‚»‚ꂼ‚ê‚ج•ھ–ى‚جگê–ه‰ئ‚ً‚½‚ؤ‚ـ‚آ‚ç‚ꂽ‚ئ“ْ–{ڈ‘‹I‚ة‚ح‹Lچع‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@گê–ه‰ئ‚ئ‚µ‚ؤپAژ›چHپi‚ؤ‚炽‚‚فپjپEکI”ص”ژژmپEٹ¢”ژژmپE‰وچHپi‚¦‚½‚‚فپj‚W–¼‚ج–¼‚ھڈم‚°‚ç‚êپA‚»‚ج‚¤‚؟ٹ¢”ژژm‚حپA–ƒ“ق•¶“zپi‚ـ‚ب‚à‚ٌ‚تپjپE—z‹M•¶پi‚و‚¤‚‚¢‚à‚ٌپjپEœ ‹M•¶پi‚è‚ه‚¤‚‚¢‚à‚ٌپjپEگج–ƒ‘ر–يپi‚µ‚ل‚‚ـ‚½‚¢‚فپj‚ج‚S–¼‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

”ٍ’¹ژ›‘nŒڑŒ¬ٹغٹ¢
–¾“ْچپ‘؛–„‘ •¶‰»چà“Wژ¦ژ؛ژû‘ •i
پiŒfچع‹–‰آٹm”Fچدپj |
پiژQچlپF”ٍ’¹ژ›’TŒںپj
پiژQچlپF”ٍ’¹ژ›گصپj
–â‚P‚Uپ@پ@پ@‰ھژ›‚ج‘nŒڑژ‚جŒ¬•½ٹ¢‚ج•¶—l‚ح‚ ‚é‰ت•¨‚ًƒ‚ƒ`پ[ƒt‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA‚»‚ج‰ت•¨‚ئ‚ح‚ا‚ê‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚PپFƒ‚ƒ‚پ@پ@پ@‚QپFƒuƒhƒEپ@پ@پ@‚RپFƒ~ƒJƒ“پ@پ@پ@‚SپFƒٹƒ“ƒS

•’“¸“‚‘گ•¶Œ¬•½ٹ¢
پiٹ¢—ًژjژ‘—؟ٹظپj |
پ@‰ھژ›‘nŒڑژ‚ةژg—p‚³‚ꂽŒ¬•½ٹ¢‚حپAپu•’“¸“‚‘گ•¶پv‚ئŒ¾‚ي‚ê‚镶—l‚إپAٹCڈb•’“¸‹¾‚ب‚ا‚ةŒ©‚ç‚ê‚é•’“¸“‚‘گ•¶‚و‚è‚حپA‘@چׂب“ثگü‚إژ}‚â–[‚ھ•\Œ»‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBڈم‰؛‚ة‹و‰و‚³‚ꂽŒ¬•½ٹ¢‚جڈم‚ةگü‹کژ••¶پA‰؛‚ة•’“¸“‚‘گ•¶‚ً”z’u‚·‚é”ٍ’¹‚إ‚à’؟‚µ‚¢•¶—l‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB |
پ@ “¯ژي‚جٹ¢‚ھڈo“y‚·‚é‘هکa“à‚جژ›‰@‚ھژRٹش‚âچ‚‘ن‚ب‚ا‚ة—§’n‚·‚邱‚ئ‚©‚çپAژRٹxژ›‰@“ء—L‚ج‚à‚ج‚¾‚ئ‰ًژك‚³‚ê‚é‚ةژٹ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚±‚جŒ¬•½ٹ¢‚حپA“ˆêگV—…پi‚U‚U‚Xپ`‚X‚R‚Tپj‚ج‰e‹؟‚ًژَ‚¯‚ؤ‚¢‚é‚ئچl‚¦‚ç‚êپA‰ھژ›ڈo“y‚ج‚à‚ج‚ھ‰نچ‘‚إ‚ح‚»‚جڈ‰Œ©‚¾‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@‰ھژ›‚حپAپu•}ŒK—ھ‹Lپvپuژµ‘هژ›”N•\پv‚ب‚ا‚ج‹Lک^‚©‚çپA‘mپE‹`•£‚ھŒڑ—§‚µ‚½‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‹`•£‚حپA‘گ•اچcژq‚ئ‰ھ‹{‚إˆêڈڈ‚ةˆç‚ؤ‚ç‚ꂽ‚ئ‚àŒ¾‚ي‚êپA‚»‚ج‰ڈ‚©‚çژ““Vچc‚ج’؛ٹè‚ًژَ‚¯‚ؤپAچcژq‚ج•ى’ٌ‚ً’¢‚¤‚½‚ك‚ةپA‰ھژ›‚ًŒڑ‚ؤ‚½‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚إ‚·‚ھپAڈعچׂح•s–¾‚إ‚·پB
‘nŒڑ‰ھژ›‚حŒأٹ¢‚جڈo“y‚â‘bگخ‚جژc‘¶‚©‚çپAŒ»‰ھژ›‚ج–ه‘O‚ًڈ‚µگ¼‚ضچs‚ء‚½‚ئ‚±‚ë‚ة‚ ‚éژ،“cگ_ژذ•t‹ك‚ةŒڑ—§‚³‚ꂽ‚ئگ„’肳‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‘nŒڑٹْ‚حپAڈo“yٹ¢‚جگ„’è”N‘م‚ئژj—؟‚ب‚ا‚ئ‚ج“ث‚«چ‡‚¹‚©‚çپA‚Vگ¢‹IŒم”¼‚©‚ç‚Wگ¢‹I‚إ‚ ‚낤‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@‚P‚جƒ‚ƒ‚‚حپA‹ك”N‚إ‚ح—¯ٹW‚ئŒؤ‚خ‚ê‚鉮چھگو‚ةڈو‚ء‚ؤ‚¢‚éˆسڈ ٹ¢‚إŒ©‚邱‚ئ‚àڈo—ˆپA‚±‚ê‚ç‚ة“چ‚ھ—p‚¢‚ç‚ꂽ‚ج‚حپA“چ‚ھ–Lڈُ‚â–‚ڈœ‚¯‚ب‚ا‚ًˆس–،‚·‚é‰ڈ‹N•¨‚¾‚©‚ç‚ئچl‚¦‚ç‚ê‚ـ‚·‚ھپAŒأ‘م‚جŒ¬•½ٹ¢‚جˆسڈ ‚ة‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB
پ@‚R‚جƒ~ƒJƒ“پA‚S‚جƒٹƒ“ƒS‚حپAŒأ‘م“ْ–{‚جŒ¬•½ٹ¢‚جˆسڈ ‚ئ‚µ‚ؤ‚ح‘¶چف‚µ‚ب‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
–â‚P‚Vپ@پ@پ@چ‚ڈ¼’ثŒأ••ا‰و‚ح‚¢‚آ”Œ©‚³‚ꂽ‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚PپFڈ؛کa‚T‚W”Nپ@پ@‚QپFڈ؛کa‚T‚R”Nپ@پ@‚RپFڈ؛کa‚S‚V”Nپ@پ@‚SپFڈ؛کa‚S‚T”N
پ@ڈ؛کa‚S‚V”N‚RŒژ‚Q‚P“ْŒكŒم‚Oژ”¼چ پAچ‚ڈ¼’ثŒأ•‚ج”Œ@’²چ¸‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚½–شٹ±‘P‹³ژپˆêچs‚حپA“گŒ@Œû‚ج‚ ‚é“ى–ت‚ًŒ@‚èگi‚ف“گŒ@Œû‚ة“’B‚µ‚ـ‚·پB’†‚ً”`‚¢‚½–شٹ±ژپ‚حپA•ا‚ة‰½‚©•`‚©‚ê‚ؤ‚¢‚éژ–‚ً”Œ©‚µ‚ـ‚·پBچإڈ‰‚حپA‰½‚©‚جٹشˆل‚¢‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئژv‚ء‚½‚ئ‰ٌŒع‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚»‚ê‚ظ‚ا‚ج‘ه”Œ©‚¾‚ء‚½–َ‚إ‚·پB‰ن‚ھچ‘‚إŒأ••ا‰و‚ھچإڈ‰‚ة”Œ©‚³‚ꂽڈuٹش‚إ‚·پB”Œ@‚ةڈ]ژ–‚µ‚ؤ‚¢‚½ٹwگ¶‚جˆêگl‚حپA“–ژ‚ًگU‚è•ش‚ء‚ؤپu‘O“ْ‚جپi‚Q‚O“ْ‚ةŒ@‚èگi‚ق—\’è‚ھ‘ه‰J‚جˆ×‚Q‚P“ْ‚ة‰„ٹْ‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½پj‘ه‰J‚جگ¦‚ـ‚¶‚³‚حپA‚ـ‚é‚إچ‚ڈ¼’ث‚ج”ي‘’ژز‚ھپuٹJ‚¯‚é‚بپv‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚¢‚½‚©‚ج‚و‚¤‚¾‚ء‚½پv‚ئکb‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@ڈ؛کa‚T‚W”N‚ح“Œ‹ƒfƒBƒYƒjپ[ƒ‰ƒ“ƒhٹJ‰€‚ج”NپBڈ؛کa‚T‚R”N‚ح“،ˆنژ›‚جژO’ثŒأ•‚©‚ç‚W.‚Wm‚à‚ج‹گ‘هڈC—…‚ھ”Œ©‚³‚ꂽ”NپBپiŒ»چف‚»‚ج‹گ‘هڈC—…‚ح‹ك‚آ”ٍ’¹”ژ•¨ٹظ‚ة“Wژ¦‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پjپ@ڈ؛کa‚S‚T”N‚ح“ْچq‹@‚و‚اچ†‚جƒnƒCƒWƒƒƒbƒN‚âژO“‡—R‹I•v‚جٹ„• ژ©ژE‚ھ‚ ‚ء‚½”N‚إ‚·پB”NŒژ‚جŒo‚آ‚ج‚ح‘¬‚¢‚à‚ج‚إ‚·پB
پiژQچlپF—V–K•¶ŒةپEچ‚ڈ¼’ثŒأ•ژGچlپj
–â‚P‚Wپ@پ@پ@چ‚ڈ¼’ثŒأ•‚ج“Vˆنگخ‚ح‚S–‡‚إچ\گ¬‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA‚±‚ج“Vˆنگخ‚ح’z‘¢ژ‚ةپA‚ا‚جڈ‡”ش‚إ‘g‚ـ‚ꂽ‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚PپF–k‚©‚ç“ى‚ض‚ئڈ‡”ش‚ة‘g‚ٌ‚¾
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚QپF’†‰›‚ً’u‚¢‚ؤپA–k‚ئ“ى‚ً‘g‚ٌ‚¾
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚RپF“ى‚©‚ç–k‚ضڈ‡”ش‚ة‘g‚ٌ‚¾
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚SپFژl‚آˆêڈڈ‚ة‘g‚ٌ‚¾
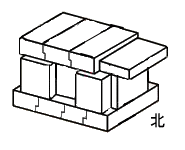
چ‚ڈ¼’ثŒأ•گخژ؛گخ‘g–حژ®گ} |
پ@“Vˆنگخ‚S–‡‚ج‘g‚ف•û‚جڈ‡”ش‚حپA“Vˆنگخ‚ةپuچ‡‚¢Œ‡‚«پv‚ئŒؤ‚خ‚ê‚é‘g‚فچ‡‚ي‚¹‚ج‚½‚ك‚جŒ@‚èچ‚ف‚ھچى‚èڈo‚³‚ê‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤ•ھ‚©‚è‚ـ‚µ‚½پB
گخژ؛‚حپA’·‚³‚XژعپA•‚R.‚Tژع‚ئŒv‰و“I‚ةگ¸چI‚ةچى‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ة‚à‚©‚©‚ي‚炸پA“Vˆنگخ‚S–‡‚ج“àپAچإŒم‚ج‚S–‡–ع‚¾‚¯‚ھڈ¬‚³‚”–‚‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB |
پ@ژ‚جچHژ–Œ»ڈêٹؤ“آ‚حچQ‚ؤ‚½‚±‚ئ‚إ‚µ‚ه‚¤پB‰½Œج‚±‚ٌ‚بژ–‚ة‚ب‚ء‚½‚ج‚©•ھ‚©‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپA‚R–‡‚إ‘S•”‚ً•¢‚¤‚آ‚à‚è‚ھگ،–@•s‘«‚إ‚ ‚ء‚½‚ج‚©‚à’m‚ê‚ـ‚¹‚ٌ‚µپA‚S–‡–ع‚ة‰½‚©“ء•ت‚جˆس–،‚ًژ‚½‚¹‚½‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB’P‚ةگفŒvƒ~ƒX‚¾‚ء‚½‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپBچ،Œم‚جŒں“¢‚ھ‘ز‚½‚ê‚ـ‚·پB
ٹF‚³‚ٌ‚à‰½‚©ژv‚¢“–‚½‚é‚ئ‚±‚ë‚ھ‚ ‚ê‚خچl‚¦‚ؤ‚ف‚ؤ‰؛‚³‚¢پB
پiژQچlپF—V–K•¶ŒةپEچ‚ڈ¼’ثŒأ•ژGچlپj
–â‚P‚Xپ@پ@پ@چ‚ڈ¼’ثŒأ•‚جگخژ؛‚ة‚حپAژ½‹ٍ‚ھ“h‚ç‚ê•ا‰و‚ھ•`‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA‚±‚ج•ا‰و‚ح‚¢‚آ•`‚©‚ꂽ‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚PپFگخژ؛‚ً‘g‚فڈم‚°‚ؤ‚©‚çژ½‹ٍ‚ً“h‚ء‚ؤ•`‚¢‚½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚QپFگخچق‚ةژ½‹ٍ‚ً“h‚ء‚ؤ•ا‰و‚ً•`‚¢‚ؤ‚©‚ç‘g‚فڈم‚°‚½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚RپFگخچق‚ةژ½‹ٍ‚¾‚¯“h‚ء‚ؤپA‘g‚فڈم‚°‚ؤ‚©‚ç•ا‰و‚ً•`‚¢‚½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚SپFگخچق‚ةژ½‹ٍ‚ً“h‚ء‚ؤپA‰؛ڈ‘‚«‚µ‚ؤ‚©‚ç‘g‚فڈم‚°‚ؤ•ا‰و‚ً•`‚¢‚½
پ@چ‚ڈ¼’ثŒأ•‚حˆê’Uگخژ؛‚ًٹ®گ¬‚³‚¹‚½ŒمپA“ى‘¤‚ج”إ’z‚ًژو‚èڈœ‚«پA“ى•ا‚ًژو‚èٹO‚µ‚ؤ•ا‰و‚ً•`‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB•ا‰و‚جٹ®گ¬Œم‚ة“ى‘¤‚ة•و“¹‚ًگف‚¯–طٹ»‚ھ”ہ“ü‚³‚êپAچؤ‚ر“ى•ا‚ًژو‚è•t‚¯–§•آ‚µ‚½گخژ؛‚ئ‚ب‚èپA‚»‚جŒم’ڑ”J‚ة”إ’z‚ھگ¬‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@گخژ؛‚ج•آچاگخ‚إ‚ ‚é“ى•اگخ‚ج’†‰›’ê•س•”‚©‚ç‚TŒآ‚ج‚¦‚®‚èŒٹ‚ھŒ©‚آ‚©‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBŒٹ‚ح•‚Wپ`‚P‚OcmپAچ‚‚³‚Uپ`‚VcmپA•‚V‚WcmپB‚ظ‚ع“™ٹشٹu‚ة•ہ‚رپAƒmƒ~‚إچي‚ء‚½‚ئ‚ف‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBڈ°گخ‚ة‚àƒmƒ~‚جگص‚ھژc‚ء‚ؤ‚¨‚èپA‚±‚ê‚ç‚ح“ى•اگخ‚ًژو‚èٹO‚µ‚½چگص‚¾‚ئچl‚¦‚ç‚ê‚ـ‚µ‚½پB
پ@•ا‰و‚ً•`‚چغ‚ة‚حپA—\‚ك‰؛ٹG‚ھ—pˆس‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½‚à‚ج‚ئچl‚¦‚ç‚êپA‰؛ٹG‚ً•ا–ت‚ة“]ژت‚µپA‰؛•`‚«پAچتگFپA•`‚«‹N‚±‚µ‚جڈ‡‚إچى‰و‚µ‚½‚و‚¤‚إ‚·پB
پiژQچlپF—V–K•¶ŒةپEچ‚ڈ¼’ثŒأ•ژGچlپj
–â‚Q‚Oپ@پ@پ@چ‚ڈ¼’ثŒأ•‚جگخژ؛‚ة‚حپAژ½“h–طٹ»‚ھ’u‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½‚ھپA‚ا‚ج‚و‚¤‚ة’u‚¢‚ؤ‚ ‚ء‚½‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚PپFڈ°گخ‚ة‚»‚ج‚ـ‚ـ–طٹ»‚ً’u‚¢‚ؤ‚ ‚ء‚½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚QپFگخژ؛‚ة‚»‚ج‚ـ‚ـˆâ‘ج‚ً’u‚¢‚ؤ‚ ‚ء‚½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚RپFڈ°گخ‚ة–طگ»ٹ»‘ن‚ً’u‚¢‚ؤ‚»‚جڈم‚ة’u‚¢‚ؤ‚ ‚ء‚½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚SپFڈ°گخ‚ةگخگ»ٹ»‘ن‚ً’u‚¢‚ؤ‚»‚جڈم‚ة’u‚¢‚ؤ‚ ‚ء‚½
 |
پ@“ڑ‚¦‚ھ‚Q‚إ‚ب‚¢ژ–‚ح’¼‚®‚ة‚¨•ھ‚©‚è’¸‚¢‚½‚ئژv‚¢‚ـ‚·‚ھپA“ڑ‚¦‚ح‚R‚إ‚·پB‚Q‚O‚O‚V”N‚WŒژپA‰ً‘جچى‹ئ’†‚ج”Œ@’²چ¸‚إپAڈ°گخ‚ةٹ»‘ن‚جچگص‚ھ”Œ©‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پBڈ°گخ‘S–ت‚ة“h‚ç‚ꂽژ½‹ٍ‚ةŒْ‚ف‚جˆل‚¤ڈٹ‚ھ‚ ‚é‚ظ‚©پAگخژ؛’†‰›•”‚إ’·•ûŒ`‚ةچ•‚•دگF‚µ‚½•”•ھ‚ھٹm”F‚³‚êپA–طٹ»‚جƒTƒCƒY‚و‚è‚àˆê‰ٌ‚è‘ه‚«‚¢‚±‚ئ‚©‚çپAٹ»‘ن‚جچگص‚ئچl‚¦‚ç‚ê‚ـ‚µ‚½پB |
پ@ٹ»‘ن‚ج‘ه‚«‚³‚حپA’·‚³‚Q‚P‚V.‚T‚ƒ‚چپA•‚U‚V.‚T‚ƒ‚چ‚ئگ„’èپA‘¤•ا‚ة•t‚¢‚½ڈگص‚©‚çچ‚‚³‚ح‚P‚V‚ƒ‚چ‚ئگ„’肳‚ê‚ـ‚µ‚½پB‚»‚جٹ»‘ن‚جڈم‚ةپAچ•ژ½‚ھٹôڈd‚ة‚à“h‚ç‚ꂽ–طٹ»‚ھ’u‚©‚êپA‘‘Œµ‚³‚ً‰‰ڈo‚µ‚ؤ‚¢‚½‚و‚¤‚ةژv‚ي‚ê‚ـ‚·پB
پ@•›‘’•i‚ئ‚µ‚ؤ“گ“ï‚ً–ئ‚ꂽ‹à“؛گ»“§ڈü‹à‹ï‚â‹à“؛گ»‰~Œ`ڈü‹à‹ïپA‹à“؛گ»کZ‰ش•¶چہ‹à‹ï‚ب‚ا‚ھ”Œ@‚³‚ê‚ؤ‚¨‚èپA”ي‘’ژز‚ھ‚¢‚©‚ةچ‚‹M‚بگl‚إ‚ ‚ء‚½‚©‚ھ‚¤‚©‚ھ‚ي‚ê‚ـ‚·پB
پiژQچlپF—V–K•¶ŒةپEچ‚ڈ¼’ثŒأ•ژGچlپj
|

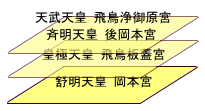


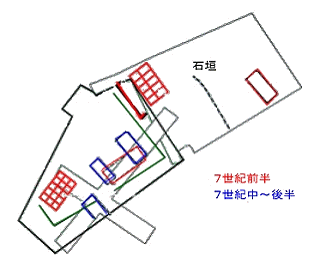
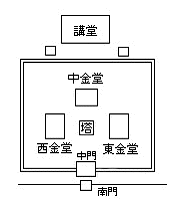
 پ@
پ@